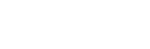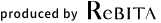――2024年11月に竣工した「TODA BUILDING」は、アーティゾン美術館に隣接する27階建てビル。低層フロアにはMUSEUM TOKYO、小山登美夫ギャラリー、タカ・イシイギャラリーなどの芸術施設や商業施設を擁し、アーティゾン美術館と共に、芸術による街づくりを目指す街区「京橋彩区」の核となる。このビルの1階にあるのが、アートギャラリーとベーカリー&カフェが併設された「Gallery & Bakery Tokyo 8分」。オープン後第2弾となる今回の展覧会は、山脇紘資さんの新作個展「玄関」(2024年12月7日~2025年1月14日)。これまで、主に野生動物の顔を大画面いっぱいに緻密に描く油彩画を発表してきた山脇さんが、今回は趣向を変え、“虚”を描く挑戦を行った。山脇さんが考える“虚”とはいったい何か?
美術教師に言われた一言が今につながっている
鈴木:このスペースは、オンラインプラットフォーム「ArtSticker」を運営する「The Chain Museum」と、「THE CITY BAKERY」を運営する株式会社フォンスの共同運営なんですよね。ビル1階の角地で、2方向がガラスの壁だから、どんな展示をしているか外からもよく見えますね。「Tokyo 8分」というネーミングもおもしろい。
遠山:東京駅から歩いて8分ということと、何かが「起こる=happen」を掛けているんです。不動産物件の案内的な計測では7分なんですけどね(笑)。ベーカリー&カフェにしたのは、付近で働く人たちの憩いの場所にもしたかったので。オープニング記念の展覧会は、友沢こたおさんの新作個展「Fragment」でした。スライムやビニール人形のぬめぬめした質感をリアルに描く彼女の絵が、街ゆく人の足を止めていました。
鈴木:大盛況だったようですね。そして今回が山脇紘資さん。すごい、絵の迫力。そしてこの詰め込み感! これまでの作品とは一味も二味も違いますね。山脇さんには、2021年にもこの連載にゲストとして来ていただいたけど(https://r100tokyo.com/curiosity/talk-art/arttalk_vol07/)、今回は山脇さんってどういう人なのかっていうことから聞きたいと思っていまして。アートを専門に学ぼうと思ったきっかけとか、そんなところから教えていただけますか?
山脇:特別面白いストーリーがなくて恐縮なんですが、大学受験が迫ってきた高校3年生の頃、美術の先生から「あなたはアートの才能あるかもね」って言われたんです。その一言を信じきって(笑)、美大だったら勉強しなくていいし、カッコいいかもしれないくらいの希薄なものです。先生が僕を見たのか絵を見たのか、それはわかりません。

遠山:そういう人、実はすごく多いね(笑)。加藤 泉さんも東京に行くための手段として、美大に行ったと言っていた。KIGIの植原亮輔さんもそうだし。
山脇:幼少期からずっと絵を描いていたとかではまったくないし、親もただのサラリーマンでした。
遠山:美大のための予備校には通ったの?
山脇:はい。当初は勉強せず軽く受かると思っていたんですが、気づいたら4浪もしたんですよね。東京藝術大学を目指していたけど、4浪目に恐ろしくなって武蔵野美術大学を受けて、なんとか版画科に補欠合格して今に至ります。首の皮一枚でつながって、大学院でようやく藝大に行けたんですが、ずっと落ちこぼれですね。
遠山:版画科に入って何をやっていたの?
山脇:版画はつまらなくて、授業中勝手に絵を描いていたんです。やさぐれたやつだと思われていたでしょうね。でも4浪もしたからこそ、1年生の頃から一生懸命ギャラリーにコンタクトを取ったり、絵を持ち込んでなんとか展覧会のチャンスをもらっては描いていたという感じです。版画はほとんどやっていなかったのですが。
遠山:浪人生のときに受験の勉強をしながら自分の作品も描きはじめたの?
山脇:そうです。3浪目くらいから、村上 隆さん主宰の「GEISAI」に出品して、動物の顔の絵で賞をいただいたりしました。僕、今年39歳なので「GEISAI」 はもう17年か18年前。ずっと動物の顔を描いてきて、最近ようやく違うものを描いていいって言われた気がして、新しく取り組んだのが今回です。長い間、主に顔を描き続けてきてあふれ出たもの、それをちゃんと絵にしたらこういうふうになりました。藝大のとき、僕の話をすごく理解してくれて、僕の絵が気持ち悪くて好きだって言ってくださったのが、恩師であるO JUN先生です。研究室に入れてくれました。

幸運な出会いから画家としての道が開けた
鈴木:アート活動を仕事にしようと決めたのはいつだったの?
山脇:思い返してみても、明確に決めたタイミングはないです。本当に運とか、誰かに出会って助けてもらった結果ですね。無責任な意味じゃなくて、今でも絵が仕事なのかどうかよくわからないです。いただいたチャンスに本気で向き合ってきて、とりあえずそれが続いてきたかたちですね。画家としてのデビューは、当時何も世に認められていない人間にもかかわらず、貸し画廊が嫌で「ZEIT -FOTO SALON」という写真を扱う老舗画廊に縁を得たのがきっかけなんです。そこの石原悦郎さんが最初の恩人です。彼が僕を中国のアート関係者などに紹介してくださったんです。
鈴木:小学館から『写真をアートにした男』という石田さんの伝記が出ているんだけど、「ZEIT -FOTO SALON(ツァイト・フォト)」は日本の写真ギャラリーの草分けなんですよ。石原悦郎さん、残念ながら亡くなりましたけど。
遠山:山脇君の絵を初めて買ったのは東京・国立の「ZEIT -FOTO kunitachi」だったよね。猿が舌を出してるやつです。
山脇:はい、遠山さんが来てくださった2021年の『estate』の展示会場は石原さんのご自宅です。実は僕、石原さんのところから一度逃げ出しているんです。「これを描け、あれを描け」って言われるのが嫌で……。
鈴木:石原さんはすごいディレクションするんだよね。鋭いし、仕事に精力的で、作家に対してエネルギッシュ。
山脇:でも今となってはものすごく感謝していますし、他にそんな人はいなかった。当時23歳くらいで、僕が若すぎたっていうのもあると思います。

遠山:アーティスト以外の可能性を考えたことってある?
山脇:ありますよ。それこそ大学院を出たばかりのとき、博報堂や電通に行った同級生から華やかなライフスタイルを聞くと羨ましく思いました。ズタボロのアトリエでひとり絵を描いている自分とのコントラストといったら。ああ、代理店に行きゃよかった!って一瞬真面目に思いました。泣きそうになりましたけど……デカい絵を何枚も描いているうちにそんなことは忘れていました(笑)。
鈴木:社会的に認知されるまでがね……。でも美大だとそのまま就職しない人もたくさんいる。そうすると認知されるきっかけがないわけでしょ。画家になって賞を取るとか、あるいは有名画廊で展覧会でもやれば社会との接点ができるけどね。
山脇:大学のキャンパスにいると、良くも悪くも社会から隔絶された感じがしました。
鈴木:まだ大学の中にいるうちはパラダイスだよ。一般大学と違ってみんな楽しそうで仲良くて。愛知県立芸大とか山形の東北芸術工科大学に行くと学生が羨ましい。でも社会との接続が難しいんだよね。東京の美大だったら、バイト先、例えばデザイン事務所とかたくさんあるけど、愛知とか山形になると、学生生活は素敵だけど、いずれ東京の美大出身のやつらと闘えるのかなって余計な心配をしてしまう。山脇君は、自分のことを信じる力が強いほうなのかな?
山脇:いえ、さっきの「決めた」ということと同じく、信じているかどうかもよくわからなくて。それよりも「生かされてる」って感じるほうが元気になります。今回の展示もしっかりオーガナイズしていただいて、力を分けてくださるスタッフや遠山さんのような存在が活力になるんです。

遠山:美術と出合ってから何か思考が深まったり、人間性が変わったりした?
山脇:たぶんもともとこういう性質だったのにもかかわらず、子どもの頃は自分で自分を差別していたんだと思いますね。お前は暗いとか、シャイなやつだとか。美術と出合ったことで変わったというよりも、何かタガが外れた。本質的には幼少期から何も変わっていないけど、今のほうが余計な束縛がなくなって楽な気はします。
遠山:今回の展覧会でも、毎日ひたすら描くっていう状況がきっとあったと思うけど、それは普通に受け入れられている感じ? 楽しいとかつらいとかはいかが?
山脇:僕にとって描くことは、どこか寝て食べて排泄する感じと似ています。排泄も気持ちがいいときもあれば、苦痛なときもある。ただ、排泄しないと死んじゃう。それと同じかもしれません。出かけるとき以外は基本的に毎日描いています。旅は海外含めて年に5、6回ぐらいは必ず行くんです。今回の展示も実は全て旅からの発想が元になっているんです。制作時間を削ってでも旅はするべきだと感じています。
西洋的な陰影でも、浮世絵の平面性でもない、新しい自分らしさ
遠山:今回会場に入って、「わ、かなり詰め込んだな」って思ったんだけど、森の中っていうか、密度のあるところに埋もれる体感があるよね。
山脇:正直、僕がもしマネジメントする立場なら、何点か外すかもしれません。新しい作品を選り好みせずにズラッと並べてみて、自分自身の目で客観的に確認してみたかった。オシャレに飾ろうという思考は捨てました。

遠山:熱量を感じるよね、これだけあると。
山脇:ただ実は、今回はベクトルの強度を増すほうから、引くほうに向けていったんです。これまではどんどん動物の質感を上げていたんですが、物質的なもののその一歩先にある空気であるとか、そういうところを表出させるために、筆の数は減らしたほうが良かったんです。自分の過去の仕事に対して負けたくないという思いはものすごくあります。
遠山:僕はあの赤いのと、この穴みたいなのがいいと思った。
山脇:赤いのは《歌枕》で、穴は《肛門》というタイトルです。今回日本語の題名に対して、全てにスラッシュがついて英語タイトルを掲げているのですが、対訳にはなっていません。《肛門 / Universe》だったり、《自画像 / Blindness》とか。肛門を描くことで、その先の内部を描くことになるっていう感覚があったり、そういう感じです。
遠山:パッと見て色のトーンが紫っぽく揃っているけど、それはたまたま?
山脇:たまたまではないです。以前から《Purple》っていう題名の作品を何点か描いていて、紫色が自分の初源の色という意識があります。紫って高貴な色でもあり、何色でも受け止める色であり、かつ受け止めた色を倍増させるような働きがあって。色学的なことでもいろいろあるんですけど、僕にとっても最も重要な色です。今回、ギャラリーの空間が持つ白い色に対して、ちょっと青みがかった紫っていうのがいい作用をするのではと思ったので、紫を基盤にしました。
遠山:そのうえに黄色も多く見られるね。
鈴木:紫と黄色は補色ですね。

山脇:そうです。互いに呼び求め合い、補う色同士です。だからその対比で、紫を見ているようで最終的には光の色を見ているようになります。モネやセザンヌなどのオーソドックスな印象派の絵の構造や仕事は参考にしています。セザンヌの水彩画は、透明色をどんどん重ねていってギリギリの不透明色をつくる。それが自分の仕事にもとてもリンクするところがあります。
鈴木:最初に描いた絵はどれですか?
山脇:この猿の2枚です。これが本来の僕の動物の絵の技法で、他の作品とはタッチが違います。この絵は国宝《桃鳩図》に触発されています。北宋時代の徽宗皇帝のものです。

鈴木:北宋第8代の徽宗皇帝が描いたとされる、個人蔵の国宝ですね。10年に1回くらいだけ、根津美術館で公開されますね。
山脇:何がすごいかっていうと、平面性と立体性、リアリズムと装飾性という、相反するものがひとつになっているところです。だから膨らんでも見えるし、平べったくも見える。この技法っていうのが、現代にどうアップデートされ得るのかっていうことを意識して、ずっと絵を描いてきたんです。独特のあの質感や膨らみを見たときに、西洋的な陰影を描いているわけではなくて、浮世絵の平面性でもない、新しい二次元的なものを感じました。ずっと僕が追求してきたものが自分の中で高みに至って、色面(しきめん)のモノ自体よりも、構図の持つ意味合いのほうが重要になったとき、心象表現ですが顔がパパッと割れて。ちょっと難しい話になってしまいましたが、そのようにして《虚/Open》って題名のあの作品が生まれたという流れです。
遠山:ではあの《虚/Open》が今回の核なんだね。

山脇:あの絵のおかげで流れができました。「虚」というと、よく「虚構」とか「何もないもの」と勘違いされるんですけど、「虚」が実体なんだと思うんです。これは古来から言われていることですが、お茶碗では茶碗そのものは本体ではなくて、お茶が入る内側の空間(見込み)が「虚」で、それ自体が本質、本体、実体なわけです。じゃあそれを絵で立ち上がらせるときに、動物の顔を描くっていうのはいわば茶碗の外を描くことであり、その中にあるそのものを表現するためにはどうすればいいかっていう議題が、あの絵から始まっているんです。遠山さんがあれを良いって言ってくださって、すごいなって思いました。あの絵は特別なので。
実際に私は毎朝毎晩茶を点てて飲むのですが、その際に茶碗の見込み=虚と対峙する感覚がこの作品にはよく表れていると思います。
鈴木:普段はけっこうストイックな生活をしていますよね?
山脇:傍から見るとそうかもしれませんが、それが性に合っているから。たとえば徹夜で描いたとしてもキツいとは思わないです。違和感がないってことですかね。納得感があるということなのかもしれません。人とも仕事とも関係し合って自分が納得しているっていう構図が今は幸せなんだろうって思いますね。
遠山:では不安なことっていうのは特にない?
山脇:現実的なことで、絵が売れるんだろうかとか、フリーランスでやっているのでそういう不安はありますよ。今後は二人三脚で歩いてくれるギャラリストと組んで、もう少し自分のステイトメントをつくっていかないと、という意識は持っています。もちろん海外も見据えて。動物は今も描いていますし、また全面に出てくるかもしれない。変えること自体に価値があるとはまったく思っていないです。
鈴木:それは正しいと思いますよ。成功している人って同世代のギャラリストと組むもの。有名ギャラリーに入りたいっていうよりも、同世代と組んで一緒に世界を獲るというケースはよくある。
山脇:遠山さんたちの存在ももちろん大きいです。本当に多くのチャンスを与えていただいているので。純粋に絵と対峙してくださり、飾りたいと言ってくださる方々の存在が、何よりも力になります。
Information

脇紘資 個展「玄関」
Gallery & Bakery Tokyo8分
会期
2024年12月7日(土)~2025年1月14日(火)
会場
Gallery & Bakery Tokyo8分
住所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 1F
営業時間
08:00〜19:00
※12月30日 8:00~17:00、12月31日 8:00~17:00、1月2日 10:00~19:00
休み
1月1日(水)
観覧料
無料
アクセス
東京メトロ銀座線「京橋駅」6番出口 徒歩3分
東京メトロ銀座線「日本橋駅」B1出口 徒歩5分
JR各線「東京駅」八重洲中央口 徒歩8分
▶Tokyo 8分公式Instagram
▶ArtSticker HP https://artsticker.app/events/49898
profile

1985年、千葉県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科を修了し、国内外で展覧会を多数開催。BEYOND THE BORDER、Tangram Art Center(上海)の展覧会をきっかけに注目される。世界的に活躍する画家のZhou Tiehaiや辰野登恵子、オノデラユキらと展示を行い、近年では森山大道、五木田智央らが出品するグループ展の参加や、北海道日本ハムファイターズの新球場を含めたエリア「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」にて2mを超す大作が公開展示された。
▶︎https://www.instagram.com/kosuke.yamawaki/
▶︎https://yamawakikosuke.com/
profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。
▶︎http://www.smiles.co.jp/
▶︎https://t-c-m.art/
profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。
▶︎https://twitter.com/fukuhen