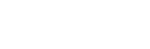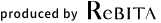「障害者」という言葉のイメージをポジティブに変える
障害があるというだけで弱者と見なされ、社会から同情すべき存在として認識される——。そういった障害者にかかっている社会的なバイアスに違和感を抱き、「障害」という言葉から連想されるネガティブイメージを変えようとしているのが、双子の兄弟が立ち上げた福祉実験ユニット「ヘラルボニー」だ。
全国の福祉施設とマネジメント契約を結び、障害のあるアーティストが手がけたアート作品をライセンス化。プロダクトやプロジェクトに落とし込み、多様な事業を展開している。

もともと双子の弟である松田崇弥さんは広告代理店でプランナーとして活躍し、兄の文登さんは大手ゼネコン会社で被災地の再建に従事していた。そんな彼らはなぜ一緒に、「福祉」を起点とした事業を立ち上げるに至ったのだろうか。
創業ストーリーを語る上で欠かせない存在が、自閉症がある4歳上の兄、翔太さんだ。

二人は自分たちと同じように泣いたり怒ったり、時には腹がよじれるくらい笑い、毎日を楽しそうに生きる兄を身近に見てきた。しかし、周りは兄を「かわいそう」と言い、自分たちに「兄の分まで一生懸命生きるんだ」と声をかけた。
「障害者という枠組みに入ってしまうと、支援するべき対象と見られてしまうのはなぜだろう。小学生ぐらいから、そういう社会の構造そのものに違和感を覚え、障害がある人のイメージを変えたいと思ってきました」と話すのは崇弥さん。

秘めた想いを形にする大きなきっかけとなったのは、崇弥さんが帰省した際、母に誘われて岩手県花巻市にある「るんびにい美術館」を訪れたことだった。そこで障害のある作家が描いたアート作品を目の当たりにしたとき、これまでにない衝撃が走ったという。
「観た瞬間にビビビッ! ときましたね。純粋にすごいなと。もしかすると、このアート作品を知的障害がある人が描いたとあえて言い切り、しっかりと発信していくことで、障害がある人のイメージそのものを変えられる可能性があるのではないかと思いました」

お互いに何かあると、すぐに電話で報告するという仲の良い二人。崇弥さんはいつもどおりに、その話を熱量をもって文登さんに伝えたという。
意気投合した二人は、アート作品をデザインに落とし込んだネクタイブランドを発表するなど、副業として事業をスタートさせた。だが取り組んでいくうちに、徐々に福祉をライフワークにしたいという想いが強くなっていったという。

「自分はネクタイブランドをやりたいわけではない。アート作品をライセンス化することで、もっと広い領域で勝負できるのではないか、と思ったんです」
崇弥さんはある日、そんな想いを抑えきれず衝動的に会社を辞め、文登さんに電話をかけた。一緒に、本気でやろうと持ちかけたのだ。
「将来性もわからないし、最初はすごく反対しましたよ」と話す文登さん。だが話し合ううちに、次第に同じ「やりたい」という気持ちになり、後を追うように会社を辞めることとなる。

こうして本格的な事業化に向けて踏み出した二人だったが、両親の猛反対にあう。特に銀行員だった父親は「そんな事業内容で融資してくれるところはない」と言い放った。そして「兄の十字架を背負わなくていいから」と泣いて訴えたという。
「会社を辞めたとき、僕らは不安よりもワクワクのほうが大きくて、これまでやりたくてもやれなかったことをやるのだというポジティブなマインドでした。だから両親のそういう反応には、正直びっくりしたんです」と二人は笑う。

次々と浮かんでくる「やりたいこと」、そして生来のポジティブな性格も後押ししたことに加え、「二人一緒」という心強さが何よりも力になったのだろう。結局、両親の反対を押し切ってヘラルボニーを立ち上げることとなった。
福祉を起点に新たな文化を創出する
「異彩を、放て。」このポジティブかつインパクトのある言葉がヘラルボニーのビジョンだ。「障害」という言葉をあえて「異彩」と定義し直し、言い換えることで、障害のある人に対するネガティブな印象を払拭したいという強い想いが込められている。
それを体現するプロジェクトの一つが、建設現場の仮囲いをアートで彩る「全日本仮囲いアートプロジェクト」だ。殺風景だった白い壁を地元の福祉施設に所属する障害のあるアーティストが描いた作品で彩り、社会にポジティブな変化をもたらす媒体として活用するというものだ。

「仮囲いのメリットは、アートや福祉に興味がない方にも、当たり前のように見て、触れてもらえるところだと思っています」と話すのは、発案者の文登さん。
さらに最近では、百貨店のバナーとして展示されていたターポリン素材のアート作品をアップサイクルし、トートバッグにするという新たな取り組みもスタートさせた。街を彩ったアート作品が、今度は人を彩るトートバッグとなり、新たな価値を創出している。

思想を宿すこだわりが詰まったプロダクト
ヘラルボニーの何よりの強みは、異彩を放つツールとしての役割を果たすプロダクトにこそある。障害があるアーティストが手がけた作品という背景を知らなくとも、単純に素敵と思えるものにすることで、発信力を高めているのだ。
それを可能にしているのが、ファッションデザイナーやマーケターなど、各業界の第一線で活躍してきたユニークな経歴を持つスタッフたち。福祉の経験こそないものの、それぞれに熱い想いを抱き、ヘラルボニーを通して新たなチャレンジを続けているプロフェッショナル集団だ。

彼らがやろうとしているのは、支援やボランティアではなく、あくまでもビジネス。純粋にいいと思ったアート作品だけを厳選し、こだわりの素材とデザインによって創り出されるプロダクトは、価値に見合う正当な価格で販売され、売り上げの一部はライセンス料としてアーティストに還元されている。
「このライセンス事業が拡大すれば、アーティストは継続的に収益を得られるようになります。プロダクトを気に入って買ってくださる方にも、障害がある人にも、事業主である我々にも嬉しい、まさに三方よしのモデルですね」と文登さんはやわらかな笑顔で話す。

現在、日本の障害がある人の賃金はまだまだ低いという。ヘラルボニーの事業が広まれば、生活が一変するアーティストが増えていくことにもなる。それこそが、彼らの目的でもある。
「あるとき、息子さんの作品の収益で、初めて家族で焼肉を食べたという親御さんから『人生で一番美味しい焼肉でした』と言ってもらえたんです。そして『初めて息子を誇らしく感じた、これからはもっと社会に連れ出していきたい』とも話してくれたんです。そういうきっかけを我々が作れているということが、本当に嬉しかったですね」
障害は、欠落ではなく、絵筆になる
緻密で繊細な線、色彩や構成の妙。ヘラルボニーのギャラリーに整然と並んだ作品には、人の心を惹きつけるパワーがある。
自閉症やダウン症のある人は、一日の中でこの時間にはこれをやるというルーティンを持つ人が多いという。そして、ルーティンは生活だけでなくアートにも反映されている。
「障害がある人のアート作品の面白さは、まさにルーティン化という特性にあると思っています」そう言って崇弥さんが見せてくれたのは、ボールペンでひたすら丸を描くことで現れた作品や、膨大な色がひしめくように描かれた作品など、どれも気の遠くなるような作業を丹念に積み重ねて創り上げられたものばかり。
それは、知的障害があるからこそ描ける世界だ、と崇弥さんは言う。

「障害」を「絵筆」に置き換えたとき、障害がある人へのリスペクトが自然と生まれてくる——これこそが、ヘラルボニーが目指すイメージの転換なのだろう。
フラットな社会の実現を目指すヘラルボニー
創業から2年余りが経った今、ヘラルボニーには彼らの思想に共感した多くの企業から次々と声がかかり、新たなプロダクトやプロジェクトが始動している。

ではこの先、ヘラルボニーが広まっていく先には、どんな未来が待っているのだろうか。
崇弥さんは言葉を丁寧に選びながら、次のように話してくれた。
「我々が手がけているのは、世の中を便利にするようなモノやコトではありません。しかし、商品に思想を乗せることで、社会の見え方や在り方みたいなものを変えていくことはできるのではないかと思っています。障害と聞いて連想するイメージが、面白い個性を持っているというプラスのものへと変化し、家族は障害がある人をもっと街へと連れ出し、自慢したくなる。社会がそんなふうに温かく変わっていくような、きっかけを作れたらいいなと思っています」

彼らが目指すのは、誰もが心穏やかに暮らせるやさしい社会だ。
将来的には、カーテンや壁紙、家具など、ファブリック全般を網羅するライフスタイルブランドを目指すというヘラルボニー。

ヘラルボニーのプロダクトが設えられた住環境は、物質的な豊かさを超越する本質的な豊かさで満たされることだろう。
ぜひ一度、美術館へ行く感覚で店頭へと足を運び、実際に作品に触れ、そこに込められた想いに心を馳せてみてほしい。
企業情報
ヘラルボニー
▶https://heralbony.com
「HERALBONY GALLERY」
どこよりも異彩を放ち、成長し続けるギャラリーを目指して、4月16日(金)よりMAKUAKEにてサポーターを募るクラウドファンディングに挑戦中(期間など詳細は下記のサイト参照)。
▶https://www.makuake.com/project/heralbony/
店舗情報
「HERALBONY SHOP」(常設店舗)
岩手県盛岡市菜園1-10-1パルクアベニュー・カワトク3階 紳士服売り場
常設店舗のほか、全国各地にてポップアップショップを開催中(期間など詳細は下記のショップリスト参照)。
▶https://heralbony.com/pages/shop-list