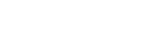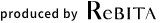日本が誇る9人の建築家展
遠山:まず、安藤忠雄さんが設計した尾道市立美術館で開催されている「ナイン・ヴィジョンズ|日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」という企画展についてお聞かせいただけますか?
白井:企画自体はチーフキュレーターの前田尚武さん(建築士、学芸員)から出てきたものです。建築界のノーベル賞と言われるプリツカー建築賞を受賞した日本の建築家8組9名を紹介している展示です。実は私は以前、マガジンハウスの編集者でした。『Casa BRUTUS』の編集者時代に、日本人建築家の活躍をもっと日本人自身が知るべきではないかと思い、「ニッポン最大の輸出品は建築家です」という特集を2度つくりました(2007年4月号|No.85と2015年12月号|No.189)。その特集でもプリツカー建築賞の受賞建築家を取り上げたりしていましたので、個人的に以前からとても興味のあるテーマでした。
鈴木:白井さんは『Casa BRUTUS』で丹下健三の特集号もつくっていますよね? あれはいつですか?
白井:2005年8月号(No.66)です。この特集は後にムックとして再編集し発売しました。ただ丹下健三さんに実際にインタビューをしたのは2000年7月号の東京特集の時でした。当時、丹下さんは86歳とか87歳だったと思います。丹下事務所のあった青山の草月会館に何度も通いましたが、毎回所員の方が優しく接してくださって、お茶だけ飲んで帰るみたいなことが続いたんです。本当のところはやんわり断られていたのですが、はっきりノーとはおっしゃらないので、鈍感な僕は断られているのに気づかず……(笑)。少し間が空いて、『Casa BRUTUS』の「柳 宗理特集」をお送りしました。そうしたら「柳さんも出ているんだね」と丹下さんがおっしゃったそうで、急に取材のOKが出たんです。ご高齢だったのでご体調が優れない日もあり、何度かキャンセルの末、無事取材ができ、「東京は丹下健三がつくった」という特集号が出来上がりました。
鈴木:今の安藤さんとか伊東さんに近いご年齢ですよね。
白井:実際には私やインタビュアーが質問しても、丹下さんが答える前に隣の番頭さんが答えちゃう。直接のやり取りは、ル・コルビュジエの質問に絡めて「国立西洋美術館をどう思われますか? 」と聞いたら、「うーん、あれは小さいね」っておっしゃったのと、ポートレートを撮るときにライティングについて「まぶしいですか?」 と聞いたら、「うん、まぶしい」と。交わした言葉はそのふた言だけでしたが。
遠山:白井さんは編集者として、建築家がもっとフィーチャーされるべきだということをずっと感じていたんですね。
白井:スポーツの世界では日本人選手が海外で活躍したり、あるいは、映画祭ならヴェネチアやベルリンの映画祭で賞をとるとビッグニュースになるのに、日本人建築家がプリツカー建築賞をとってもそれほど大きく報道されることはないですよね。例えば谷口吉生がMoMAの改装、坂 茂がポンピドゥー・センターの分館、設計事務所SANAAがルーヴル美術館の別館を手がけていたりするわけですが、広く知れ渡ってはいない。そんな悔しい思いがあって、『Casa BRUTUS』で孤軍奮闘、建築の特集に力を入れてきました。いわば、それが今回の企画や展示の原形になっているのかもしれません。
鈴木:「ナイン・ヴィジョンズ 」では、プリツカー賞を受賞した8組(9名)、丹下健三、槇 文彦、安藤忠雄、妹島和世・西沢立衛[SANAA]、伊東豊雄、坂 茂、磯崎 新、山本理顕の仕事がそれぞれ違った要素で集められていて、レファレンスできる。出品交渉も調整もさぞや大変だったことと思います。最終的によくひとつの会場に集めたと思いました。
白井:皆さん著名な建築家の方で、お一人でも美術館で個展を開催できるビッグネームの方ばかりです。それをひとつの展覧会で紹介してしまうというのはすごく贅沢なことだと思います。建築専門誌の人などに話すと「そんな大変なこと誰もやろうと思わないよ」という反応でした。確かに誰かに忖度(そんたく)していたら何もできないですよね。もしかすると丹下さんをインタビューしたときのような私の鈍感力が幸いしたのかもしれません(笑)。
鈴木:そもそも『Casa BRUTUS』での活動自体が大変だったでしょうし。古くからある建築雑誌の秩序の中に、ライフスタイル雑誌が建築をテーマにして、分け入るというのは。編集者として当然やりたいという情熱があるけれど、取材される側の建築家にも、既存の専門誌にも立場があるし。
白井:今回の出展交渉についてももちろん時間はかかりましたが、建築家の方々にご協力いただける連絡をいただけた時の喜びは何物にも代えられません。2週間前、坂 茂さんがトークイベントを行ってくださることが突然決まり、昨日、尾道へ来てくださいました。急な話だったので大きな会場が押さえられず、結局和室しかない建物の大広間に座布団を敷いて、100人くらいで坂さんを囲んでトークを聞きました。この講演会のためだけに飛行機で広島まで来てくださって。東京だったら絶対あり得ない座布団トーク。それだけに聞く方も真剣でした。
遠山:それはいい話だなぁ。
白井: 伊東豊雄さんもおっしゃっていましたが、日本の建築家の特徴は系譜がたどれることでしょうか。出身校・師弟関係もはっきりしていて、比較的、建築家同士が仲がよいのも特徴ではないかと思います。
鈴木:歴代のプリツカー賞受賞者も丹下健三にはじまり、ちょっとした系譜がありますよね。横のつながり、縦のつながりがあって。一匹オオカミの多いアーティストとは異なる点ですね。
遠山:今の日本の主な輸出品って、浮世絵、舞踏、アニメ、コム デ ギャルソン、そして建築だね。そのなかでも大きくて、我々が体感できるのが建築。
鈴木:国宝や重要文化財指定のお寺などがある千光寺山の中の尾道市立美術館で、世界で活躍する日本の建築家が紹介されていたり、そうかと思えば、福山市の神勝寺という広大な敷地のお寺のスペースを借りて、今後、ますます活躍が期待される若手建築家の展示があったり、今回の建築祭は「建築歴史図鑑」「建築家人名録」みたいになっているのがいいなと思いました。展示を本に例えて言ったけど、本より優れているのは、実物だったり、立体の模型だったり、映像だったりが展開されているところだな。
土地の特徴を生かした建築
遠山:新作ということでは、キオスク(小さな仮設建築)が3つ、尾道市と福山市にありましたね。おのおのインフォメーションセンターだったり、グッズショップだったり、お茶のスタンドになっている。堀部安嗣さん、石上純也さん、中山英之さんがそれぞれ地元の企業とコラボする形で。
白井:建築に興味がない人でも、通りがかったときに「これはなんだろう」と気にしてくれる建物がないといけないと思い実現した企画です。福山駅前には石上純也×常石造船×ツネイシカムテックスによる「雲がおりる」、尾道の戦時中に建てられた海運倉庫だった建物をリノベーションしたONOMICHI U2前の広場には中山英之×モルテンによる「風景が通り抜けるキオスク(Catch)」、神勝寺 禅と庭のミュージアム(無明院)の一角には、堀部安嗣×ウッドワンによる「つぼや」があります。いずれも小さな仮設の建築ですが、建築祭開催中しか見ることができないのでぜひ現地へ足をお運びください。
鈴木:そのほかに我々が見てきたものを順番に解説していただけますか? 尾道市立美術館からさらに5分くらい登った山頂にある「展望台PEAK」。
白井:あれは2022年に青木 淳さんの設計でつくられました。前にも展望台はありましたが、一般的な円塔で、たくさんの人が同時に上がれるところではなかったんです。「PEAK」はらせん状+全長63mの長い廊下が付いていて、多くの人が思い思いの場所で同時に遠くを眺めるという、新しいタイプの展望台だと思います。天気がよければ、尾道水道や日本遺産である尾道の街並み、さらには四国のほうまで見えます。標高約144mの千光寺山の頂上からみんなで一斉に風景を見て、「あれが見えた、これが見えた」などと話をしながら下りてくる楽しい体験ができます。
遠山:そこから山を下る途中で「OPEN LLOVE HOUSE|尾道『半建築』展」を見ました。会場のLLOVE HOUSE ONOMICHIは建築家の長坂 常さんが手に入れた一軒家ですが、以前改装中に来たことがあります。庭に露天風呂があって。あそこに浸かって尾道の街を眺めたら気持ちがいいでしょうね。
鈴木:いい具合に古色を帯びた家屋ですが、結構、手は入れていますよね。天井板なども全部新しくなっていました。2階の窓からの眺望がなんといっても素晴らしい。いい場所ですよね。長坂さんの今後のクリエーションにも期待が高まります。
白井:築110年の建物で、海側にかしいでしまっていたのを構造体にも一部手を入れ修繕しています。見えない部分でかなりお金がかかっているし、随所に工夫が施されていますよね。今回の展示としては長坂さんの建築事務所であるスキーマ建築計画が、創立以来27年間に携わったプロジェクトや現在の活動する内容です。普段は開放されていませんが、建築祭期間中は2階でお茶を飲んでいただけますよ。
遠山:車も入れない崖のようなところによくぞ家屋を建てたと思います。

白井:元の建物はかつての地元の有力者というか、お金持ちの人が別荘として使っていたものだそうです。普段住む家ではなくて、ときに芸者さんを呼んだり、仕出しをとって人を接待したりする場所とのことで。あの家の横にある平屋は作家の志賀直哉が逗留(とうりゅう)し、『暗夜行路』を書いた家でした。千光寺山自体が、そのように富裕層が別宅を建てて余暇を過ごしたり、文化人が逗留するような場所だったんです。
建築のテーマパークのような神勝寺
遠山:7万坪という広大な敷地をもつ神勝寺はどんな寺なのでしょう?
白井:もともとこの場所は、臨済宗建仁寺派の特例地で寺院としては1965年の創建なので比較的新しいものです。常石造船の社長であった神原秀夫氏が、禅師を開山に招請し建立しました。船の事業では、海難事故や不慮の事故で亡くなる人が少なくないため、慰霊の念が込められています。敷地には各地から移築してきた建物があり、臨済宗中興の祖と称される江戸中期の禅僧、白隠慧鶴(はくいんえかく)の禅画や書のコレクションがあります。そして、彫刻家の名和晃平率いるSandwichの設計した「洸庭(こうてい)」が2016年に建てられました。伝統的な杮葺(こけらぶき)の技法を応用して、全体をサワラ材で柔らかく包んだ舟型の建物です。内部は、光と波によるインスタレーションを通じた約20分間の瞑想的な体験ができる空間になっています。
遠山:「洸庭」は建築なのか、アート作品なのかどちらなんだろうという疑問が頭をよぎりました。映像が具体的にどう映されているのか、実際に何を見せられているのか詳細にはわからなかったけど、ある種の揺らぎがあって、まるで巨大な船に乗っているような感覚にもなりました。
白井:造船と深く関わりのある場所なので、海や船を感じていただけるのはアーティストの意図するところであると思います。建物の周辺に敷かれた石は海原を表現し、植栽はプラントハンター・西畠清順さんによるもので、たとえばソテツワラビは波から頭を出す魂のようなイメージだそうです。
鈴木:全長約45メートルの巨大なフィナンシェのような形が印象的ですね。これだけの大きさは必要なのかなと一見思いますが、おそらく必要なんですよね。白井さんが丹下健三を取材したとき、国立西洋美術館について「あれは小さいね」とおっしゃったそうだけど、建築家にとって建物の大きさというのは重要な要素なのでしょう。権威を誇示したり、宗教の施設などは機能との関係を超えて、大きさが重要になる。国立西洋美術館も後になって地下に拡張しているのは機能の問題ですが。
遠山:神勝寺の無明院で展示している「NEXT ARCHITECTURE|『建築』でつなぐ新しい未来」の展示も意欲的なものでした。
白井:〈ひろしま国際建築祭〉の展示はすべて、総合テーマ「つなぐ——建築で感じる私たちの“新しい未来”」を踏まえて企画されています。そのなかでもここでの展示が一番ストレートに、総合テーマを体現しているのですが、「海」「⾃然」「市⺠」「⾵景」「宇宙」という5つの視点から未来のあり方についての提案がされています。いずれも建築と社会の新たな結びつきを探るものであり、建築がいかにして私たちの未来を形づくるかを問いかけています。出展建築家は藤本壮介さん、石上純也さん、川島範久さん、VUILD/秋吉浩気さん、そしてNYを拠点に活動するClouds Architecture Officeです。
鈴木:総門に一番近いところにある「松堂(しょうどう)」と名づけられた寺務所は建築家で建築史家の藤森照信さんによる設計ですね。建物に沿って庇(ひさし)が長く伸びているのが特徴的ですね。
遠山:建物が外部と内部を明確には分け隔てず、グラデーション的なたたずまいですよね。しかも雨や夏の強い日差しが避けられる。
鈴木:10年くらい前、遠山さんと細川護熙元首相の湯河原の窯場に取材に行ったことがありましたね。実はここを見て、同じく藤森さんが設計したあの建物を思い出していたんです。
遠山:懐かしいですね。芳雄さんと初めて仕事をしたときだね。『BRUTUS』で。
鈴木:ここ神勝寺に今後新たにできるものはありますか?
白井:今、長坂 常さんが宿坊を計画しています。
建築は知的好奇心を満たすメディア
鈴木:最後に改めて、この建築祭の魅力と、これから来場する方へのメッセージをお願いします。
白井:今月11月30日まで開催されていますので、栄えある第1回にぜひ来ていただき、のちに「あの建築祭の初回に行ったんだよ」と自慢してください(笑)。オリジナリティが高く、また力のこもった「ナイン・ヴィジョンズ」や「NEXT ARCHITECTURE」などの展示はもちろんですが、LOGやONOMICHI U2、神勝寺 禅と庭のミュージアムなど、展示会場自体の建築も素晴らしいので、空間体験自体も楽しんで欲しいです。そして、この土地の空気を吸って、この地域ならではの美味しいものを食べ、美しい海や山の風景を堪能してもらえればと思います。
遠山:ちょうど牡蛎(かき)もシーズンだしね。紅葉も始まり、目にもご馳走でしょう。
白井:瀬戸内国際芸術祭や周辺の町や島、美術館などと組み合わせた旅程も可能かと思います。3年後に開催予定の第2回の話を少しすると、丹下健三自邸「成城の家」(1953年完成/現存せず)を福山市内に再現するプロジェクトが進行中です。今回はその予告展ということで、宮大工が制作した縮尺3分の1 模型を神勝寺の無明院・明々軒に展示しています。原寸大再現に関しては実施図面が残っていないものの、写真を徹底して集め、家族の記憶をたどり、鋭意進行中です。また、建て替えのため休業している「ベラビスタ スパ&マリーナ 尾道」も2027年リニューアルオープン予定なので楽しみにしていただければと思います。
遠山:こちらほどの大規模ではなく、ささやかなものだけど、私も建築と地域活性のプロジェクトを北軽井沢で進行中なので、今回の建築祭はそのことと重ね合わせて考えるよい機会になりました。芳雄さんはどう感じましたか?
鈴木:繰り返しになりますが、久しぶりに編集者・白井良邦の名仕事を見せてもらったと思いましたね。雑誌と違って、今回は読者を現地に招き入れ、実物を見て形状や大きさを体感してもらい、五感をフル稼働してもらうための編集。旅は一次資料に触れる絶好のチャンスですね。土地の天候や訪れる時間帯というエレメントも入るので偶然性や一回性も高い。空間や建築そのものが、知的好奇心を満たす上質なメディアになっていると感じました。
白井:「ひろしま国際建築祭」では、歴史や物語のあるものをリノベーションして付加価値を与えることや、アーキツーリズムを通じて新たな価値を再発見する大切さを共有するというのが主眼のひとつです。尾道市と福山市を舞台に、長く土地に根差した古い建物や、それらを気鋭の建築家がリノベーションしたユニークな建築が会場になっているので、何日か滞在していただき、できるだけ多くのことを体験していただきたいです。
鈴木:白井さん、どうもありがとうございました。

リンク「ひろしま国際建築祭2025」
▶︎https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
profile

神原・ツネイシ文化財団理事|慶應義塾大学SFC 特別招聘教授|Sustainable Japan Magazine by The Japan Times 編集長。1993年出版社マガジンハウス入社。雑誌『POPEYE』『BRUTUS』を経て雑誌『Casa BRUTUS』には1998年の創刊準備から参加。2007年~2016年『Casa BRUTUS』副編集長。建築や現代美術を中心に担当する。2017年〈せとうちクリエイティブ&トラベル〉代表取締役就任。客船guntû(ガンツウ)など富裕層向け観光事業に携わる。2020年編集コンサルティング会社〈アプリコ・インターナショナル〉設立、同社代表取締役。著書に『世界のビックリ建築を追え』(扶桑社)、共著に『この旅館をどう立て直すか』(CCC メディアハウス)、『Shiroiya Hotel Giving Anew』(ADP)ほか。瀬戸内エリアの観光や文化振興を考える「瀬戸内デザイン会議」メンバー。
profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。
▶︎http://www.smiles.co.jp/
▶︎https://t-c-m.art/
profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。
▶︎https://twitter.com/fukuhen