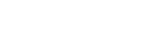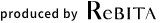大山街道の宿として栄えた道玄坂
渋谷の街はこの連載の1回目で「公園通り」を中心に取り上げたが、今回は道玄坂から桜丘のほうを散策してみたい。
僕の学生時代(主に1970年代後半)は、パルコの出店とともに公園通りが渋谷の若者の筆頭人気エリアになった時代だったが、街としての歴史が古いのは道玄坂のほうだ。たとえば、昭和初めの東京案内書の名著・今 和次郎の『新版大東京案内』の“盛り場”の章には、銀座、浅草、神楽坂、新宿、上野、人形町界隈、という順で各町の評判の飲食店などが紹介されているが、人形町の次は「道玄坂」となっており、渋谷の項目はない。国道246の旧道ともいえる大山街道(相模の大山詣に由来する)の道玄坂は、渋谷の駅ができる以前から、宿(しゅく)として栄えた場所だったのだ。


ハチ公広場にある西口に出て、109が立つ二又の左手の上り坂からがいわゆる道玄坂のイメージだが、町名としては右手のセンター街のほうまで道玄坂とついている。109を右、左にTOHOシネマズ渋谷を見て、渋谷発祥のカレー屋「いんでいら」や牛たんの「ねぎし」なんかが入った道玄坂センタービルの角を右折すると、レンガ建ての台湾料理店「麗郷」がある。

この辺は公園通りがトレンドだった学生の頃から、たまに遠征してきた。とくに、麗郷の前から真横に上がっていく石段道は思い出深い。風俗店の看板が目に入る裏ぶれた石段坂だが、『メイド・イン・USAカタログ』という『ポパイ』の前身誌が出てアメカジ的なファッションがハヤリ始めた大学1年生の頃、リーバイスのジーパンやコンバースのスニーカー……などのアメリカ輸入衣料を売る「ミウラ&サンズ」(シップスの前身)という店が、石段坂の左側にできたのだ。ここで緑色のコンバース(チャック・テイラー)のローカットのやつをゲットしたことはいまでも鮮やかに記憶しているが、当時僕は8ミリ映画を作ったりするサークルに入っていて、自ら監督・出演もした映画のロケでこの石段坂を使った。カメラマンの指示に従って、T字になった坂上の右手のほうから出てきて石段を何度も下り上りしたことを昨日の出来事のように思い出す。
“昭和感”を満喫できる百軒店
さて、石段坂を上ったT字を左に行くと、百軒店のブロックに入る。表の道玄坂のほうから入ってくると、すぐ右側に「道頓堀劇場」というストリップ劇場があるけれど、この名はオープンする(70年代初め)ときに看板屋がカン違いして書いてきたのが発端……だと昔ここの場主から聞いたことがある。



その先から「日」の字のように区画された一帯には、名曲喫茶の「ライオン」や隣のロック喫茶「B.Y.G」をはじめ、昔ながらの佇まいの飲食店がいくつか残っていて、渋谷でもとりわけ“昭和感”が満喫できるエリアといえるが、大正12年の震災の頃に、ここにあった中川伯爵の大邸宅を買い取って開発を手掛けたのは箱根土地開発(その後の西武グループ)の堤 康次郎。当初は住宅地にするプランもあったそうだが、「百軒店」という商業地的なネーミングを施して、飲食店や劇場を呼びこんだ。先の『新版大東京案内』にはこうある。
「この一廊(かく)は、震災直後、箱根土地会社の手によって出来上がったもの、道に石畳、そゞろ歩きの足も軽く、すべてが今までとはがらりと変った近代風景。カフェーもはじめてカフェーらしい。資生堂分店。正一位千代田稲荷の赤い大鳥居、こゝには実に不似合きはまる存在だ。ユングフラウ、ピヤングから曲れば渋谷キネマと聚楽座、渋谷駅のホームから、やゝ大袈裟にいへば、ツェッペリンの格納庫のやうに見えるのがそれ。」

いまの百軒店には劇場はないけれど、1960年代くらいまでは、ちょっと道幅の広くなった2つ目の筋にテアトル系の劇場があった。僕が初めてこの辺に来た頃は、後身のボウリング場があったはずだ。しかし、今 和次郎が「近代風景」と評している百軒店が「レトロ」な場所となり、不似合いとくさされていた千代田稲荷が絶妙な風情を醸し出しているというのもおもしろい。
桜丘まで広がっていた大和田町
百軒店の西側の坂を下ると、Bunkamuraのほうから来る通りに行きあたる。ひと頃は三業通りと呼ばれていたけれど、グーグルマップには「ランブリングストリート」と表示されている。ラブホテルとクラブが目につく道を南下すると、道玄坂上交番前の交差点に出る。

五、六差路のような辻のマークシティのほうから来るプロムナードの脇に、与謝野晶子の歌碑とともに道玄坂の由来碑が置かれている。ここに大和田道玄という人物にまつわる一説(山賊として旅人から金品を奪った)が記されているが、この人の行状はともかくとして、大和田の姓のほうもかつては南方の桜丘のほうまで広がる町名に採用されていた。

ちなみに、この由来碑の脇に口を開けたプロムナードは井ノ頭線のホーム横から出ていた玉電の専用軌道だった筋。ここから玉川通りの路面に出てきて三軒茶屋のほうへと進んでいく。僕が中学1年の春に廃止されたのだが、1969年5月10日のサヨナラ運転の日、知り合ったばかりの鉄道好きのクラスメイトとこの交差点のすぐ先にあった「上通(かみどおり)」の電停あたりで写真を撮ったことを思い出す。

道玄坂交番前の交差点をそのまま直進していくと、やがて246の広い道にぶつかる。車は桜丘の側に進めるけれど、人は地下道を渡らなくてはならない。上に首都高が通っているこの246(玉川通りの新道)が開通したのは1960年代の初め頃で、その時代の邦画を観るとよく工事現場がロケ地に使われている(日活と東映が多い)。東映とも関係の深い東急の本社がこの向こう側(いまはセルリアンタワー)にあるけれど、その裏側を通っている湾曲した道は古い。緩やかな坂道を下まで行かずに南方に曲がると、上階にプラネタリウムを設置した「渋谷区文化総合センター大和田」という施設があるけれど、この前身は区立の大和田小学校。明治、大正の時代はこのあたりまで大和田町で、つまり桜丘は昭和の初めに考案された、割と新しい瑞祥(イメージ的)地名なのだ。

柳並木の坂上に立っていた日本会館
渋谷の駅のほうから一直線に上がってくる道は「さくら坂」と名づけられて、桜並木が続いているが、この道が敷設されたのも60年代の初め頃だ。クレージーキャッツの『大冒険』という映画(65年・東宝)で植木 等がこの坂上にあった「日本会館」という同潤会風のアパートに住んでいるという設定になっていたが、映像をよく見ると当時は坂の並木も桜ではなく柳なのだ。
桜丘は「日本会館」をはじめとして、中庭を設けたような戦前建築のアパートや下宿洋館が多かった地域だが、そういうシブいクラシック館はもはや消え失せた。

インフォスタワーの前をさらに東奥へ進むと、ヤマハが入ったビル(ここも「渋谷サクラテラス」の一棟のようだ)の前にクネッとV字に曲折した急坂がある。かつて、このヤマハの一角に「エピキュラス」というライブや演劇をやる小劇場があって、70年代の終わり頃、東京ヴォードビルショーの公演などをよく観にきたものだ。崖になっていた線路側の一帯の景色はガラリと変わってしまったが、急カーブの坂道はそのまま残っていて、懐かしさがこみあげてきた。

泉麻人のよそ見コラム

百軒店入り口の看板建築
今回の散歩では、「麗郷」の横道のほうから百軒店にアプローチしたが、道玄坂をもう少し進むと、百軒店への入り口の反対側あたりに10年ちょっとくらい前までこういう3階建ての看板建築の建物が6軒ばかり残っていた。いまこの一帯は少し坂下のほうまで含めて大々的な再開発工事が進んでいる。
この写真、データによると僕が撮影したのは2011年5月16日で、もうこの時点で多くの店が閉業している感じではあるけれど、廃屋化しながらもこの後2、3年はがんばっていたはずだ。昭和初めの道玄坂をとらえた写真にこの建物群が写っていたのを見たことがあるけれど、神保町の古書店街などでもよく見られたこの種の建物は関東大震災後の商店建築のハヤリとされている。
ところで、一番手前(左側)の黄色い幌が軒に出た家はセキネテーラーという洋服屋だったところで、ここの息子のセキネ君は僕の大学のサークルの1年後輩だったのだ。卒業して何年も経った90年代の頃だったと思うが、一度何かの用で訪ねていって、マンサール屋根の下の『魔女の宅急便』に出てくるような屋根裏部屋を見せてもらった記憶がある。
6軒が残っていた頃は、3階建ての商店の並びを基準にして、昭和初めの道玄坂の町並みを想像したものだったが、その当時は道端に植わったケヤキももっと低かったのだろう。
profile

1956(昭和31)年、東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、東京ニュース通信社に入社。『週刊TVガイド』等の編集者を経てコラムニストに。主に東京や昭和、カルチャー、街歩きなどをテーマにしたエッセイを執筆している。近刊に『昭和50年代 東京日記』(平凡社)。