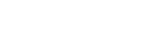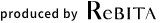なぜ、広島が舞台なのか?
「建築」で未来の街をつくり、こどもの感性を磨き、地域を活性化させ、地域の“名建築”を未来に残す――そんなミッションを掲げた「ひろしま国際建築祭」(主催:神原・ツネイシ文化財団)が今年から始まった。今後3年ごとの開催となるトリエンナーレを目指す。現在、広島県福山市、尾道市の7つの会場で開催中の「ひろしま国際建築祭2025」のテーマは「つなぐ―『建築』で感じる、私たちの“新しい未来” Architecture:A New Stance for Tomorrow」である。
建築祭展示会場の一つである「神勝寺 禅と庭のミュージアム」(福山市)で、総合ディレクターを務める白井良邦氏をゲストに、建築祭の理念、なぜ広島という土地で行うのか、今後建築祭が目指すところ、などについてお話を伺った。
鈴木:ひろしま国際建築祭、楽しみにしていました。まず、広島×建築という掛け合わせが成立する理由について教えてください。
白井:いくつか挙げられますが、歴史をずっとさかのぼると、この地域は昔からとても豊かな土地で、瀬戸内海は文化や人の交流の大動脈でした。遣隋使、遣唐使の時代、都は畿内地方にあったので、大陸へ赴くとき必ず瀬戸内海を通る。江戸時代には日本海を航路として北海道と行き来する北前船や九州船が寄港するわけです。船の動力として風や潮の満ち引きを利用していた時代、潮と潮がぶつかり、引き潮に乗せて船を運ぶ“潮待ちの港”というものがありました。その一つが福山市の“鞆(とも)の浦”という港で、貿易の要衝地でした。
遠山:宮崎 駿さんのアニメ『崖の上のポニョ』の舞台にもなった風光明媚(ふうこうめいび)なところですよね。

白井:ここ一帯にはお寺も多く、実は国宝や重要文化財の建造物がたくさんあるんです。尾道市にある浄土寺もその一つ、本堂と多宝塔は国宝で、小津安二郎監督の映画『東京物語』の撮影が行われたことでも知られています。そのような豊かな文化的土壌が連綿と培われてきた地域であることをまず念頭に置いていただければと思います。
鈴木:写真家の高野(こうの)ユリカさんが浄土寺や尾道の路地などを撮影し、文章も加えた作品を、旧三井住友銀行尾道支店を改修した「まちなか文化交流館『Bank』」で展示していましたね。土地、街、建築を通して過去から現在へとつながる時間軸と人間の絶えぬ営みを感じました。
白井:そういう展示も見ていただきたいですし、実際に空間体験もしてほしい。現代建築を体験すると同時に、国宝や重要文化財を有するお寺なども回っていただけると、さまざまなことが五感で感じられてとてもいいと思います。現代建築については、県内には今回会場となっている場所以外にも、丹下健三による広島平和記念公園および広島平和記念資料館(現在は総称して広島ピースセンター)、村野藤吾による世界平和記念聖堂、黒川紀章による「広島市現代美術館」、與謝野 久による「ひろしま美術館」(以上、広島市)その他、公民問わず優れた建築がたくさんあります。それは先ほど申し上げた文化的に豊かな土地であるということと不可分です。
鈴木:今回、自分の中で建築の知識を予習、復習できました。古いものを見られたのもよかったし、日本が誇るプリツカー賞建築家たちのおさらいができたし、若手建築家の考えに触れて、未来を垣間見た感じがします。建築家の川島範久さんにも偶然お会いできて、最前線の建築家は地球環境をどう守ろうとしているのかを知ることができたり……。
丹下健三から始まった戦後の街づくり
遠山:オープニングの伊東豊雄さんのトークではどんなことが語られたのでしょう?
白井: 10月5日のトークでは、伊東豊雄さん、石上純也さん、今回の建築祭のポスターにもなっている火星プロジェクトのチームClouds Architecture Officeに登壇いただきました。ただ、バルセロナ在住の写真家・鈴木久雄さんの登壇を予定していたのですが体調の関係で来られなくなってしまい、その代わりに若手の川島範久さんとVUILDの秋吉浩気さんに急きょトークをしてもらいました。会場はとてもホットな雰囲気になりました。伊東さんは、去年11月の東京での記者会見にも来てくださって、その時に「戦後日本の建築は瀬戸内から始まった。そのエネルギーが今も続いているんです」と話してくださったんです。伊東さんは1964年10月の東京オリンピックのときに大学を休んで、瀬戸内を回ったそうです。もちろん、目指すは丹下健三の広島平和記念公園で、やはりあそこが原点なんですよね。日本の戦後の建築の。
鈴木:原爆で大きな被害を受けた広島ですが、そこに日本の現代建築のパイオニアである丹下健三が復興に尽力した。その後も多くの建築家が連なり、都市が再生していったんですね。戦後の復興の象徴が広島であり、建築家で言うと丹下健三であり、ここで建築祭が行われる理由がよく分かりました。
白井:1928~1959年の間、建築家が集まるCIAM(シアム)という国際会議がありました。イギリスのホッデスドン大会に前川國男と丹下健三が行き、広島平和記念公園の計画を発表したら、世界中が驚いて、「日本に丹下というすごい建築家がいるぞ!」とル・コルビュジエを含め、その存在を印象づけたことがありました。数年後の1955年、原爆投下からちょうど10年目に広島平和記念公園がオープンするんです。この陳列館(現・本館)建物のピロティから慰霊碑を通して、その先に原爆ドームが見える。その南北の視点が“平和の軸線”と呼ばれるものです。当時はどちらかというと壊そうという意見も多かった原爆ドームが、平和の象徴として現存するのは、丹下健三が広島計画の中に軸線を通じて、原爆ドームを取り入れたからでしょう。
建築家と地域の持続的な連携
遠山:白井さんがこの建築祭と関わられてから、どれくらいでしょうか?
白井:建築祭の発起人は、神原・ツネイシ文化財団の代表理事の神原勝成さんです。10年以上前から、建築文化を発信する建築祭のようなことをしたい、と周囲に語っていました。「もし何かこの地域で建物を建てるなら、有名建築家に社宅やホテルを依頼すべきだ。それが積み重なれば、国内外から見に来る人がいるだろう」という義兄・末松亜斗夢さんの助言もあり、2010年くらいから社宅やホテルなどを建てるとき、建築家を起用しはじめました。当時、僕は雑誌『Casa BRUTUS』の編集者だったのですが、若手建築家の方々を紹介したのがご縁で知り合いました。それがこの建築祭にまで発展してきたという感じでしょうか。
遠山:そこから15年かけて実現させたんですね。すごいです。

白井:神原・ツネイシ文化財団は常石グループ傘下の財団ですが、その中核企業である常石造船を考えてみると、造船業というのは労働集約型なんですね。元来はアメリカやヨーロッパ中心だったものが、日本に移り、中国と韓国に移り、どんどん人件費が安いほうに生産地が動いて行く。そんな企業がどうしたら、次の100年、200年を地域と共にやっていけるか。いくつかある案の中で、実験的に取り組んでいるのが、建築を利用した観光で、僕は“アーキツーリズム”と言っていますが、要は建築を起爆剤とした町おこしなのです。建築で街を刺激するわけですが、新しく建てるばかりではなく、既にある建物をリノベーションして新しい価値を与えて人を呼び込むということもそのひとつです。2014年にONOMICHI U2、2018年にLOG(いずれも常石グループ所有)といった宿泊施設もオープンし、建築のハードの部分はだいぶそろってきたので、次はソフトにあたる建築祭のような建築文化を発信するイベントをやってはどうか、ということで、総合ディレクターとしてお声がけいただきました。今から2年半前の2023年春だったと記憶しています。
遠山:今はリニューアルのため閉館中とのことですが、高級リゾート「ベラビスタ スパ&マリーナ 尾道」は前からあったんですか?
白井:ここは元々、船主のための迎賓館として使われていた宿泊施設でした。船を発注すると、船主は調印式や進水式など、何度も現地に来る機会があります。どの造船会社もある程度の規模のゲストハウスを持っているのですが、それを泊まれるようにしたのは2000年ぐらいだそうです。そして2010年に街のシンボルになるようなチャペルをつくりたいということで、建築家の中村拓志さん(NAP)をご紹介しました。「施主が長く伴走できる、同世代の若い建築家の方がいいですよ」とお勧めしたんです。例えば安藤忠雄さんと直島など、建築家とクライアントが長く付き合って、その地域を活発化させていくことを知っていましたので、それがとても大事だと思ったわけです。
鈴木:ベネッセの福武總一郎さんが安藤さんに直島の相談をされたのは、80年代後半ですね。ベネッセハウス開館が92年でしょう。今年も安藤さん設計の直島新美術館ができました。なんと長い付き合い。
白井:この地域では、施主と建築家の良好な関係が構築されていると思います。藤本壮介さんも常石グループの社宅「せとの森住宅」を設計して以来、ひろしま国際建築祭でも展示している「海島」プロジェクトなどで関わっていますね。
おりづるタワーという祈りの場
鈴木:有名建築家の作品が増えれば、それを目指して世界中から建築が好きな人たちが見にきてくれるでしょう。地域を広げて見てみれば、直島ももちろんある。大原美術館がある倉敷はここから電車で40分ぐらい。広島には訪れるべき広島ピースセンターや「おりづるタワー」がある。地域として豊かで、建築もたくさん面白いものがあるので、数日かけて巡回するアーキツーリズムには最適な地勢ですね。
遠山:昨日、我々は広島市のおりづるタワーに行ってきましたよ。いやあ、感動しました。最初に12階で折り紙で鶴を折って、広島城側を見ていたときは、「この景色があまりにもいいので、2010年に広島マツダが買い取りました」という広報の方の説明があまりピンとこなかったんだけど、最上階の展望エリアから原爆ドーム、広島ピースセンターを眼下に見て驚きました。静かな祈りの場になっていますよね。
鈴木:原爆ドームの向こうに陽が沈む時間でしたね。逆光で。
白井:夕方がいいですよね。強く光が入ってきて、傾斜の木造のデッキを照らして。
遠山:屋上の上に木造をそのまま建てたのかなとか、いろいろ想像するとすごいことをやっているんだなって。人工物と自然が絶妙なバランスで唯一無二の空間を生み出しています。
鈴木:この場所でしかありえないみたいな場所でした。あの高さでしかありえない。
白井:今は高さ制限があるので、あの周辺に高いビルは建てられません。原爆ドームって、普通、見上げるもので見下ろすものじゃないでしょ。あの視点で見られる場所はほかにないですよね。ちなみに、折った鶴を12階から「おりづるの壁」に投入する。そうすると、ファサードのガラス張りになっている部分に積み重なった折り鶴が壁のようになって見えるという演出です。あれは最初の計画ではなかったそうですが、社員たちがつくりたいと言い出して、タワーの改修を担当した建築家の三分一博志さんに実現させてもらったそうです。
今後の開催を見据えて
遠山:そもそも建築祭って3年ごとにやっても、そこにある建物は変わらないわけだから、普通考えるとあまり変化がないように思うけど、今後はどう発展させていきますか? 今回新作の中山英之×モルテン社による移動式キオスク、石上純也さんの移動式キオスク「雲がおりる」(案内所・チケット取扱所)なんかもめちゃくちゃ良かったね。石上さんのは、造船の技術を使って約2センチに薄く叩いた鉄板が微妙なバランスで3点自立している。「雲」と銘打っているように不思議な軽やかさがあって。
白井:次回からはソフトをどのように充実させ、体験をどのように変化させていくのかがポイントかと思います。僕は『Casa BRUTUS』の編集者として、ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の取材を2004年からずっとしてきました。コロナ禍以外は全て行っています。2年に1度、いつもの場所に世界中から建築関係者が集まる国際的な建築展です。総合ディレクターが代わり、テーマが変わり、それに対して、各国のパビリオンの展示が応え、常に新鮮なビジョンを示しています。とても参考になりますね。
鈴木:国別のパビリオンもそうだし、アルセナーレ・ディ・ヴェネチア(中世の造船所跡)での展示も、中身をどんどん変えていきますよね。

白井:日本でもほかに建築祭って結構行われているんですよ。京都モダン建築祭、神戸建築祭、東京建築祭、イケフェス大阪などなど。そこでは、普段見られない建築をその期間中、ガイド付きで見られるというのが主流です。私が考えているのは、そういうものだけではなくて、毎回テーマを決めて、大勢の人が展示を通じて、ビジョンを共有できる場とすることです。未来に対して何かポジティブなものを常に発信する。3年後の第2回の建築祭については既にアイデアは練り始めていますが、ハードの面でもベラビスタホテルの完成や、丹下健三の「成城の家」の再現もあり、新たな建築ができますので、見どころは増えると思います。
遠山:でも今後存在感を増していくだろう「ひろしま国際建築祭」の初回に行った!という経験は後々自慢になるだろうね。
白井:ありがとうございます。今回はまずは私たちがやりたいと思っていることをストレートに出しました。文化庁、広島県、福山市、尾道市が後援で入ってくれていますが、今後はより親密な関係で連携できるはずです。建築祭そのものの催しや展示もさることながら、豊かな海の幸や山の幸、穏やかな時間の流れと瀬戸内海の景色を味わいに、ぜひいらしてください。
鈴木:今回、編集者・白井良邦の新たな仕事を見た、という思いがします。2都市、8会場、23組の建築家が参加する「ひろしま国際建築祭2025」について、次回【後編】では具体的な展示内容や見どころについて、引き続きレクチャーをお願いします。
リンク「ひろしま国際建築祭2025」
▶︎https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
profile

神原・ツネイシ文化財団理事|慶應義塾大学SFC 特別招聘教授|Sustainable Japan Magazine by The Japan Times 編集長。1993年出版社マガジンハウス入社。雑誌『POPEYE』『BRUTUS』を経て雑誌『Casa BRUTUS』には1998年の創刊準備から参加。2007年~2016年『Casa BRUTUS』副編集長。建築や現代美術を中心に担当する。2017年〈せとうちクリエイティブ&トラベル〉代表取締役就任。客船guntû(ガンツウ)など富裕層向け観光事業に携わる。2020年編集コンサルティング会社〈アプリコ・インターナショナル〉設立、同社代表取締役。著書に『世界のビックリ建築を追え』(扶桑社)、共著に『この旅館をどう立て直すか』(CCC メディアハウス)、『Shiroiya Hotel Giving Anew』(ADP)ほか。瀬戸内エリアの観光や文化振興を考える「瀬戸内デザイン会議」メンバー。
profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。
▶︎http://www.smiles.co.jp/
▶︎https://t-c-m.art/
profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。
▶︎https://twitter.com/fukuhen