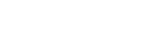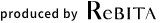120年続く老舗の店主との出会いが愛用のきっかけに

食、工芸品、旅……さまざまな分野の目利きとして知られる小山さん。もの選びの基準は「使い心地がいいもの」「“経年優化”しているもの」であることだという。そんな小山さんが手放せずにいるもののひとつが、創業から120年の歴史を誇る一澤信三郎帆布のかばん。服装やシーンにかかわらず、常に何かしら持ち歩いている。
「買ったときに一番かっこいいものよりも、使うことによってかっこよくなっていくもののほうが好きなんです。一澤帆布(現・一澤信三郎帆布)の商品を大学時代に最初に購入したのも、そういうものの中で手の届く範囲のもの、買えるものがそれだったという感じです。そのときに買ったのは、普通のトートバッグだったような気もしますし、ペンケースみたいなものだったような気もします。本格的に一澤信三郎帆布のかばんばかりを使うようになったのは、京都で仕事をするようになった14、5年前からかな。店主の一澤信三郎さんという人に出会ったことがきっかけです」
一澤信三郎さんとの出会いは「本当に偶然」だったそうで、「あるとき京都の街を歩いていたら、『あんたくまモンやった人やろ?』って声をかけられたんです。それで、『今度くまモンでこういうの作ったんや』って、くまモンが付いたバッグを見せられて。といっても、それ自体は僕の全然知らないところで作られたものでしたけどね(笑)」とのこと。
「しかもその後、京都にいるときのための部屋を決めたら、なんと信三郎さんと同じマンションだった(笑)。今では何だか、父親と同じマンションに住んでいるような感覚になっています。信三郎さんと一緒にいると、“適当に生きること”を学べる。適当というのは“良い加減”のこと。独特の余白がある気がします。普通どんなビジネスも、だいたい目標値があるじゃないですか。今年はこのくらいだったから、来年はもう少し売り上げを伸ばさなければいけない、みたいな。でも、信三郎さんにはそういう発想がまったくないんですよね。作ったものを売れればいい、という感じ。僕は成長ばかり追い求めることがあまり好きではありません。信三郎さんのところは企画会議もないんですよ! 新製品を定期的に出さなきゃいけないという恐怖感もないし、今年はこれだけ売り上げるという目標も特に立てないそうです」

実際、一澤信三郎帆布のカタログを見ると、その型数の多さに驚く。経済効率だけを考えていたら、こうはならないだろうと思わせるバリエーションの豊かさ。その背景には、同社のものづくりの考え方がある。
「職人さんがときどき、『こういうデザインを考えました』って信三郎さんのところに持っていくんですよね。すると信三郎さんは『じゃあ作って自分で使ってみ』って言う。で、1年か2年使わせて、『それでどうやったん?』って聞く。そうすると、その職人さんが『ここをこうしたらもっと便利かもしれません』と言うじゃないですか。そうすると『うん、じゃあそれで出そうか』となる。そういう感じのビジネススタイル。それが僕はすごく好きです。売り上げのために作るんじゃなくて、本当にそれを使いたい人がいるから作るというのがね」
修繕したりカスタマイズしたりして使い続ける喜び
小山さんがものを選ぶとき、経年優化に加えて重視しているのが、使い古したり、また壊れたりしても修繕してもらえること。一澤信三郎帆布は、その部分もきちんとカバーしている。何年たっても飽きないデザインだから、また長く使うごとに魅力を増すものだから、直しながら使い続けたいというファンが全国にいるのだ。
「お客さまがボロボロになってきたものを持ってきたら、それをちゃんと修繕してあげる。また古くなったら、また修繕する。一澤信三郎帆布のかばんって、その営業姿勢みたいなものも含めて、僕にとっては何か精神的なお守りみたいなものなんですよね。今日持ってきたかばんも結構修繕してもらっているんですよ。トートバッグやカメラバッグは底が破れてきちゃったから別の布で直してもらったり」
50個以上であればオーダーメイドも可能。小山さんは自身の会社、オレンジ・アンド・パートナーズの10周年記念パーティーでゲストに配布したかばんに自社のネームタグを入れたり、小山さんが立ち上げ、初代家元を務める「湯道」用に、狐桶と呼ばれる片手桶やタオルなどを入れられるバケツ型の「湯道かばん」を作ったりもしている。
「バケツ型バッグは京都市のふるさと納税の返礼品『魔法のどんぶり』を入れる“手提げどんぶり鞄”としても作ってもらっています。これを持って下鴨茶寮やイノダコーヒーとかに行くと、裏メニューを出してもらえますよ! あと、ショルダーバッグにはいつも愛用するライカのカメラとレンズを入れて持ち歩いているんですが、あまりにもいいので、ライカの社長に『コラボモデルのカメラバッグを作ったほうがいいですよ』って勧めました。そしたら、実際に彼らはひと回りかふた回り大きいショルダーバッグをベースに作ったんですよ。もちろんそれは買いましたけど、僕にはちょっと大きすぎたので、結局元のほうを使い続けています」
また、バッグではないが、小山さんがプロデュースする2025大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「EARTH MART」では、一澤信三郎帆布製の巨大暖簾とエプロンを採用していたりも。そんなふうに一澤信三郎帆布を愛してやまない小山さんだが、「この頑固な感じ、変わらない一途さは、京都の老舗のひとつのスタイルだと思う」とも話す。小山さんは京都という場所にも惚れ込んでおり、2012年に老舗料亭、下鴨茶寮の経営を継承。2017年からは京都芸術大学の副学長も務め、今では1カ月のうち7〜10日は京都にいるという。
「京都は、家を出て地下鉄の駅に歩いて行くまでの間に、いろんな商店の人と『おはようございます』とか『最近どうですか』などと挨拶を交わす街です。東京ではなかなかないじゃないですか。そんなふうに、自分と誰かとの距離が近いのが京都の魅力。あとはブレない感じかな。そういうのが一澤信三郎帆布の持つ魅力とすごく重なるんですよね」
愛着とは、自分の持ち物に愛を着せること
さて、小山さんが経年優化するものへの思い入れを強くしたのにはいくつかのきっかけがあったそう。そのひとつが20代後半での出会いだった。
「26、7歳のときにポルシェを買ったんです。それでサーキットでレースをするクラブに入ったのですが、そこに僕よりも10歳以上年上の人が——当時はおじさんに見えたけれど、考えてみれば40代だったんですよね——、1周何分で走るかを自分の時計で測っていました。その時計がロレックスのデイトナだったんですよ。 しかも、ポール・ニューマンモデルか何かの、めちゃくちゃ高いやつで。僕が『うわあ、デイトナなんか持ってるんですね!』って言ったら、その人は『これ、中学生のときに親父にもらったんだ』って。それを聞いて、いいものを手に入れてずっと使い続けるっていうライフスタイルって、すごく素敵だなと思いました」
大切な人から受け継いだものや贈り物には、それにまつわるストーリーがある。一方、自分が買ったものにも、使い続ける中でストーリーが書き加えられていく。
「やっぱり付き合い方によってそのものの価値は決まっていくと思います。僕は“愛着が湧く”という言葉がすごく好き。“愛を着せる”って書くわけですよね。 自分が持っているものに愛という衣を着せてあげるみたいな感じがするんです」
小山さんが“愛を着せる”ものの条件は「使い心地がいいもの」。愛着を感じるがゆえ、なかなか捨てられないものもあるそうで、「十数年使っているバスタオルなんかは捨てられないんですよ。そろそろ全部、ふかふかの新品に買い替えたいんですけど」と笑う。


クルマも住まいも、新しいものより年季の入ったものをチョイス
愛すべきものに囲まれて暮らす小山さん。クルマ好きとしても有名だが、「ほかのものと同じで、クルマも乗り始めたら長いです」と話す。
「1991年に買ったレンジローバー クラシックは今もありますし、2004年に買ったアストンマーチン DB9はうちの副社長に安く売ったけれど、『あなたが死んだらただで戻して』って約束付き(笑)。実は最近、初めての日本車としてレクサスのLBXを買ったんですが、運転しやすすぎてこれじゃ自分がダメになると思い(笑)、1989年式のBMWも手に入れました」
そんな小山さんは、家に関しても「住んできた家もほとんど中古マンション」という。
「東京に住むんだったらマンションのほうがいいなと思うんです。新築への憧れもあるけれど、これまでも中古マンションはスケルトンにして、好きな建築家にリノベーションしてもらってきたので、別に新築や戸建てへの強いこだわりはないですね」
最後に、小山さんが住まいに求めるものを尋ねてみると「やっぱりいい風呂かな」との答えが返ってきた。
「いい家は風呂のいい家。温泉が出ていたらなおいい。浴槽にもこだわりたいですね。あとは風が気持ちいい家でしょうか。そんな家が、国内に限らずいろんな場所にあるのが理想。夏の京都は暑すぎますし、季節ごとにいろんな場所を転々としているのが一番幸せじゃないかな」

profile
1964年熊本県天草市生まれ。日本大学藝術学部在学中に放送作家として活動を開始し、これまでに『カノッサの屈辱』『東京ワンダーホテル』『ニューデザインパラダイス』など、斬新な番組を数多く企画・構成。『料理の鉄人』『トリセツ』では国際エミー賞を受賞した。また、初の映画脚本となる『おくりびと』では2009年に第81回米国アカデミー賞外国語映画賞を受賞。文化庁「日本博」企画委員、農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員などを務めるほか、熊本県のPRキャラクター「くまモン」のプロデュース、京都市「京都館」館長など、地域創生プロジェクトに数多く関わる。EXPO 2025 大阪・関西万博ではテーマ事業プロデューサーを担当。下鴨茶寮主人、京都芸術大学副学長。株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ、N35インターナショナル代表取締役社長。
▶︎https://orange-p.co.jp/