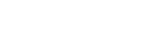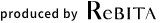奈良晒の商いから始まった、変化と進化の300年
奈良晒(ならざらし)は鎌倉時代に起源があるとされる、苧麻(ちょま)を用いて織られる高級な麻織物。1478〜1618年にかけて興福寺の塔頭(たっちゅう)・多聞院で3代にわたり書き継がれた日記『多聞院日記』には晒に関する記述があり、既に寺院に麻布が納められていたことがわかっている。なかでも天正19年(1591年)の「甚四郎、般若寺サラシヤへ婿入了、女ハ廿一才、甚四郎ハ廿四才」という記述は、当時、般若寺あたりに晒屋があったことの証左。この頃、清須美源四郎という人物が従来の晒し法を改良したことから、その用途は僧尼の法衣や茶巾のみならず、武士の裃(かみしも)などにも使われるようになった。
17世紀前半には江戸幕府によって「南都改」という朱印を受け、御用布として保護されるように。これによって奈良晒は産業として大きく成長、17世紀後半から18世紀前半にかけて、生産量はピークを迎えている。そんな奈良晒全盛期の1716年(享保元年)に、初代中屋喜兵衛が奈良晒の卸問屋として、現在の奈良本店のある元林院町にて創業したのが、中川政七商店の始まりだ。

「創業から今年で309年になるのですが、その間に結構いろんな商売をしてきたみたいです。そのなかでずっと続けていたのが麻の商い。もともとは卸商だったのですが、明治維新以降に製造拠点が激減し、奈良晒の生産量が減ると、自社工場を構えて製造卸として商売をしていた時期もあったりして。戦後の高度成長期に人件費が高騰して、国内での製造が難しくなったときには、11代中川巖吉はあくまで“人の手で作る”ことを優先し、韓国や中国の、まだ手仕事が残っているところに目を向けます。そこと協業しながら生地を作り、整理加工や染めを滋賀や京都でするようにしたんです」

14代目社長の千石あやさんは、309年続く中川政七商店で、初めて創業家以外から社長になった。彼女にとっても、中川政七商店の歴史は意外性に満ちたものだったという。
「同じことをずっとやってきたわけではないんですよね。12代中川巌雄のときには、もともと麻で茶巾をずっと作っていたことから、茶道で使われる仕覆をはじめとした茶道具を手がけるようになりました。こういうものを作ると端切れが出るのですが、それもまた非常に貴重なものなので、捨ててしまうのはもったいない。そこで巌雄の妻で13代の中川 淳(以下、千石さんの発言内では中川)の母、みよ子のデザインで、のれんやコースターなどの麻小物を作り始めます。その拠点となったのが、1985年(昭和60年)にはじめたギャラリー兼ショップ『遊 中川』です。移転によって空き家になっていたかつての中川家の住居兼商いの場でスタートしました」

みよ子が細々ながら生活雑貨の製造と小売を始めたことは、その後の同社の方向性を決定づける、大きな出来事となった。
「『遊 中川』では、今では『生活工芸』で知られる輪島塗の赤木明登さんの個展や、骨壺を集めた「THE END」という企画展を開催していて、時代を先取るような企画も多かったようです。ただ、会社の主幹事業はお茶道具で、生活雑貨のほうは利益が出ているような状況ではまったくなかった。そんな折に、2002年に富士通から中川が転職し、こっちのほうをなんとかしようということで、中川が手伝うことになったんです」
日本の工芸の未来を考えた、13代の大改革
2002年に奈良に戻った中川さんは、まず赤字続きだった「遊 中川」の業務改善に注力。生産管理というものづくりの基礎から抜本的に改革をしていった。そしてものづくりの想いを正しく伝えるための直営店を出店することが必要だと考え、「遊 中川」の直営店の出店を加速。2003年には「粋更kisara」ブランドを設立し、2006年には表参道ヒルズに旗艦店をオープンする。さらに2007年、中川さんは「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを発表。付き合いのある産地のメーカーがどんどん廃業に追い込まれている状況を鑑み、奈良に限らず日本全国に点在する300の産地が元気になる未来を目指す事業を立ち上げる。社長に就任したのは、その翌年の2008年のことだ。

「かつて『遊 中川』の赤字を改革したように、私たちの経験やノウハウは、他の工芸メーカーの方々にも役に立つのではないかと考えたのが、うちのコンサルティング事業の始まりです」
最初に手がけたのは、長崎県波佐見町の産地問屋、有限会社マルヒロの再生だった。今も中川政七商店で人気のロングセラー「ブロックマグ」でおなじみのブランド「HASAMI」は、中川さんのコンサルティングを受けたマルヒロの現社長、馬場匡平さんが2010年に立ち上げた。
「当初、うちの社員の多くは、当社がコンサルティングをすることの意味にピンと来ていなかったようです。お店で商品が売れることが、どう工芸メーカーの役に立っているか、実感する機会がなかったんだと思います。後年、馬場さんが会社にやって来てコンサルによってどれだけ会社が元気になったか、それは経営改善だけでなく、日々お店でHASAMIの商品が売れることの積み重ねなんだ、と話をしてくれたことがあって、それでようやくみんなが『そういうことだったのか!』と納得したくらいです(笑)」
「HASAMI」に続き、株式会社タダフサ(新潟県三条市)の「庖丁工房タダフサ」、株式会社 漆林堂(福井県鯖江市)の「お椀やうちだ」などのブランドを次々と成功させることで、コンサルティング事業は中川政七商店の柱のひとつに。そしてこのコンサルティングの内容を1社ずつではなく一度に多くの事業者にもシェアするべく、2016年から「経営とブランディング講座」という講座形式で全国で開催している。2011年にはコンサルティングによって生まれたブランドの流通サポートの場として、工芸の世界では初めての合同展示会「大日本市」もスタート。当初4社だった参加ブランドも、2025年には100を超えるまでに成長している。
工芸と産地の魅力を伝える「接心好感」の店づくり
中川政七商店が大事にしてきたことのひとつが、広く日本各地の工芸や文化を届けるための店舗づくり。扱う商品も「遊 中川」で小売を始めた当初は布物中心だったのが、現在では食品、器、インテリアまで、さまざまなアイテムに広がっている。一方、ブランドは2010年に誕生した「中川政七商店」にほぼ一本化し、わかりやすさを追求してきた。
店舗設計にも中川政七商店らしさは表現されている。2021年に創業地に隣接する形で誕生した「鹿猿狐ビルヂング」内には、2024年、奈良の魅力をさまざまな角度から発信する「奈良風土案内所」を設置。中川政七商店のスタッフが厳選した奈良県内のおすすめスポットを紹介する無料の「風土案内カード」は特に人気だ。ここでは中川さんが始めた、ものづくりの現場に人を呼び込むことで産地そのものを盛り上げようという同社の挑戦、「産業観光」のきっかけとなるような試みを展開。「おいしい食べ物やいい宿があれば、訪れるうえで大きなモチベーションになりますよね。そういうスモールビジネスも含めて盛り上げていきたいんです」
さらに、2024年春にオープンした栄 中日ビル店や、2025年春にオープンした福岡天神店では、日本各地の素材や建築資材に造詣が深い名古屋の設計事務所イランイランに内装デザインを依頼。より工芸を身近に感じられるような店づくりにも挑戦している。「特に旗艦店のような場所では暮らしのなかに工芸があるさまを体験できる場所を作ってほしいとか、工芸を感じられるような素材を盛り込んでほしいなどとリクエストしています」。一方、接客については以前から変わらぬ「接心好感」という言葉を掲げている。
「『接心好感』とは、お客様の心に寄り添って汲み取りながら、心地よい店舗体験を提供することで、商品、お店、ブランド、会社を好きになってもらうということ。私たちは手仕事で作られたひとつひとつの商品の魅力をお伝えしたいけれど、お客様はそれを求めていないかもしれないですよね。だから、お客様一人一人をよく見て、楽しくお買い物していただくために必要なお手伝いをする。その空気感や距離感をフォローするのが『接心好感』という言葉。それこそが“中川政七商店らしさ”かもしれません」
創業家以外からの初の社長へのバトン
さて、中川政七商店が創業300年を迎えた2016年、淳さんは13代中川政七を襲名。しかし、そのわずか2年後、彼は千石さんを社長に指名する。2011年の入社後、生産管理や社長秘書、企画課長、ブランドマネジメント室長などを歴任した千石さんのバランス感覚の良さが評価されてのことだったが、同族経営でやってきた中川政七商店の社長が中川家以外の人になるのはもちろん初めて。千石さんは驚き、最初は固辞したという。それでも、当の中川氏は意に介さなかったらしい。
「『中川家が永代続く、みたいなことはまったくなくていい』と。最初にブランドを立ち上げたみよ子も『いいんじゃない?やりなさい。でも大変だと思うから、体には気をつけてね』とお守りをくれたりして(笑)。中川との約束は、『すべての事業において必ずビジョンを上位概念に置くこと』のみ。『300年の歴史を背負うとか、社員の生活を背負うとか、そういうことを自分は考えたことがない。だから千石さんも考えないでいい』とも言ってくれました。それですごく気が楽になったんです」

就任の際、13代から14代へのバトンタッチは「トップダウンからチームワークへの変化」だと語った千石さん。中川政七商店というチームの仲間たちと手を取り合い目指すのは、さらに明るい工芸の未来だ。
「国内製造であるとか、うんと小さいメーカーにも継続的に商品を発注するとか、そこはもう完全に死守すべきこと。工芸って基本的に分業制なので、サプライチェーンのどこかが崩壊すると物が作れなくなってしまうので、産地支援は絶対です。それ以外については、世の中の空気を感じ取りつつ、常に新しい風を吹かせ続けたい。これまであまり語ってこなかった、『日本の工芸が元気になったら生活者にはどんないいことがあるのか』について言語化することも意識しています」
そんな千石さんは、「最近は、地方に移住してものづくりをはじめとした仕事に就くという人も出てきました。特に工芸の仕事は暮らしに近い。夕方まで仕事をして、食事を作って、食べ終わったらおしゃべりして。大金持ちにはなれないかもしれないけれど、そうやって無理なく生きることは、今みんなが求めている暮らしのあり方のひとつのような気がしています。もちろん、工芸が商いとして成り立つことが前提になりますが」とも。千石さん自身も入社を契機に奈良に移住して以来、ずっとこの街で暮らしている。
「大阪には夜中でも闇がなかったけれど、奈良は本当に暗くて、最初は怖くて落ち着かなかったくらい。でも、自転車通勤をするようになり、季節の変化をはっきり感じられるようになりました。本社メンバーの7割は県外から奈良に移住しているのですが、庭や畑のついた家に住んでいる人も多いので、会社のキッチンテーブルにはよく野菜や果樹がおすそわけとして置かれています。普通の毎日が豊か。ちなみに子どもが生まれると男性社員はほぼ全員、半年程度の育児休暇を取得しています」

日本の誇る古都で地に足のついた暮らしをしながら、次に千石さんたちが目指すのは海外展開。2030年の海外旗艦店オープンを目指して、今はアジア、ヨーロッパで候補地を検討中だという。その前段階として、2025年9月にはロンドンにてポップアップストアをオープンする。
「日本の工芸を世界中の暮らしのなかへ届けるための、最適な解像度を今まさに探っているところです。これに合わせて2025年からロゴもリニューアル。新ロゴにはアルファベットのブランド名や、『SINCE 1716 NARA JAPAN』の文字が入っています」
千石さんと中川政七商店は日本の工芸の価値を100年先へとつなぎ、それによって人々の暮らしを豊かにするべく、実直に、しかし大胆かつ軽やかに前進し続ける。
profile
株式会社中川政七商店 代表取締役社長。1976年、香川県生まれ。大阪芸術大学を卒業後、1999年に大日本印刷株式会社に入社し、大阪でデザイナーや制作ディレクターとして勤務。2011年に株式会社中川政七商店入社。生産管理、小売のスーパーバイザー、社長秘書、企画課長、ブランドマネジメント室長などを経験したのち、2018年に14代社長に就任。奈良については「学生時代から神社仏閣が好きでよく来ていました。あとは河瀨直美監督作品が好きで、人生の一時期にでも奈良に住めたらいいなと思っていました」とのこと。