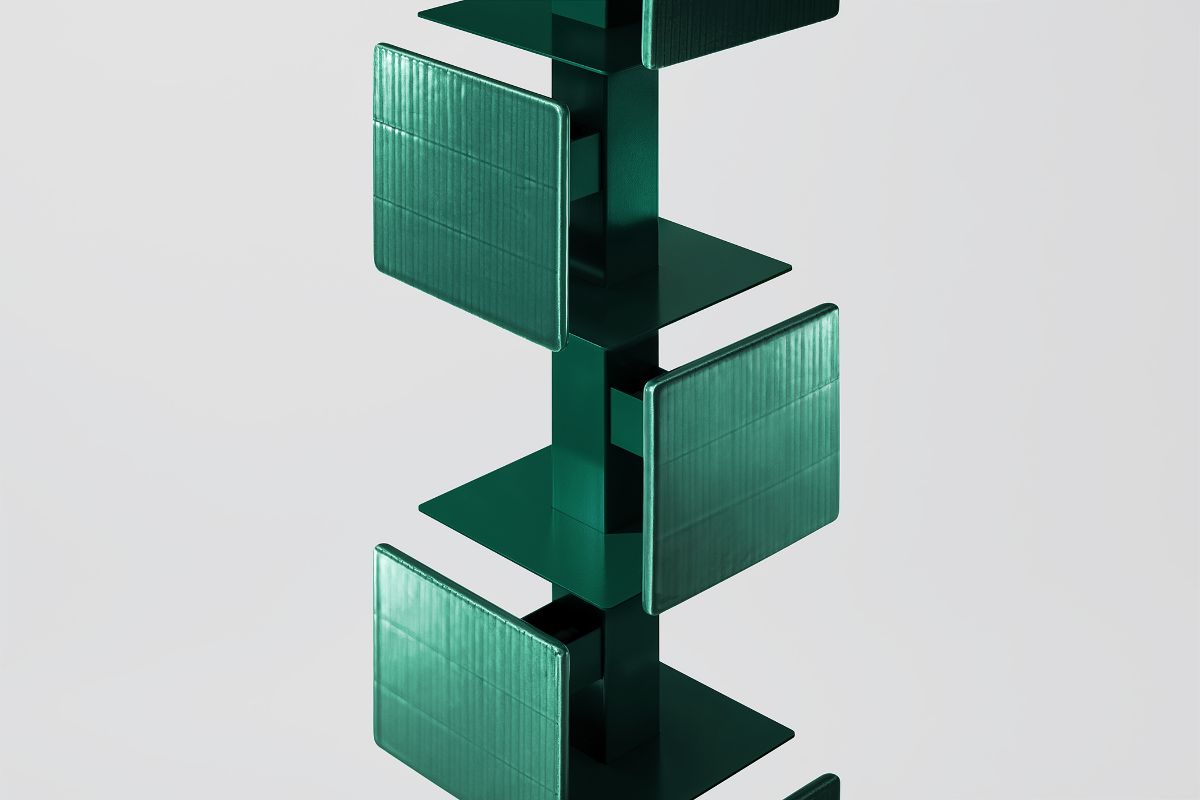鈴木氏は美大卒業後、インハウスデザイナーを経て2012年、自身のデザイン会社「プロダクトデザインセンター」を設立。同社設立以前に「Tokyo Midtown Award」審査員特別賞を受賞していた「富士山グラス」がその後商品化され話題になってからは、身近な日用品をはじめとしてさまざまなデザインを手がけてきた。19年に相模鉄道の車両をデザインした際は、20世紀前半に一世を風靡し「口紅から機関車まで」のキャッチフレーズで知られるデザイナー、レイモンド・ローウィを思い浮かべた人も多かったのではないか。時代背景も創作環境も異なる2人を単純に比べることはできないが、対象とするデザインの領域の幅広さについては首肯せざるを得ないだろう。最近では工芸の手仕事に着目すると同時に、そこに先端テクノロジーを掛け合わせたものづくりに挑戦するなど、活動の幅はさらなる広がりをみせている。

富士山グラス / 菅原工芸硝子 Photo ©️2012 PRODUCT DESIGN CENTER
時代を超えて残っていくものの強さとは
——「幼少期、古美術収集家の祖父の感化を受けた」とおっしゃっていますが、お祖父様はどのようなものを収集されていたのでしょうか? また、彼からどんな影響を受けたとお考えですか?
祖父が収集していたのは主に日本と東アジアのもので、土器から器、書画、刀剣のほか、民芸品のようなものまでいろいろありました。時代も江戸時代のものから、比較的現代のものでは魯山人の作品までさまざまでした。
祖父の部屋にはそうした古美術品が大量に並んでいて、部屋を訪れると一つひとつ丁寧に説明してくれました。そうやって過ごしていくうちに、子どもながらに考えたこと、発見したことが2つありました。ひとつは、時代を超えて残っていくものってなんだろうということです。もちろん子どもですから、突き詰めて考えたわけではなくぼんやりと感じたことですが、残っていくものの強さの本質を追求することは、今でも僕がデザインするときに大切にしているテーマです。

もうひとつは、特に日本の工芸品に見られる季節や風土の表現です。たとえば、祖父は刀剣の鍔(つば)もたくさん集めていて、そこにはトンボやさまざまな自然のモチーフが描かれている。また、お椀にも四季折々の図柄が描かれていたり、夏茶碗、冬茶碗という使い分けがあったりする。そうした風土とともにあるモノの豊かさに感心したというか、面白い発見でした。
——時代を超えて残っていくものに関心があったとおっしゃいました。これは「過去のものづくりにヒントがある」とする鈴木さんの考え方にもつながりますが、それはプロダクトデザイナーとしての活動においてどのように生かされていますか?
デザイナーの基本的な姿勢として、僕はものづくりの歴史、文化をとても重視しています。人類初のツールといわれる「ハンドアックス(旧石器時代の握斧)」さえも、シンメトリーを意識して形の美しさを追求していたように僕には見えます。それがナイフの原形となり、時代を経て現在の包丁に進化してきた。
モノというのは急激には進化しません。僕が常に心がけているのは、そうやって延々と時を経て残ってきたモノを未来へと着実に、あるいは適切につなげることです。そのためにはそのモノの過去を振り返り、残ってきた理由、その本質を見極める必要がある。僕自身も100年後も残っているようなデザインをめざしています。

それから僕にとって、時代を超えて今も残っているものは単に「古いもの」という言葉では括れません。伝統工芸の技術も現在のものづくりとつながるので、そこに新旧はない。たとえば最新の3Dプリンティング技術で磁器を成形し、それに釉薬をかけて普通の焼き物のように焼成することで作品を作る。そうやって昔からある技にその時々の先端テクノロジーをかけ合わせてきた結果、現在があるのではないかと思っています。
ローカリティの突出から個性的で魅力的なものが生まれる
——大企業やビックメゾンとお仕事をする傍ら、日本や世界の地場産業や伝統工芸の職人さんたちとも積極的に協業をされ、「ローカリティとテクノロジーの融合」を追求されています。その発想の原点についてお聞かせください。
僕がデザイナーとしてのキャリアをスタートさせたのが、ちょうどiPhoneが日本で発売された頃で、大量生産の最後の時代だったように思います。それから15年くらいの間に社会はずいぶんと変化して、20世紀的なユニバーサルなものづくり、皆が同じモノを使うのが楽しい時代は終わり、自分だけにフィットするもの、個性的でとがったものが求められるようになった。自ずと中量・少量生産になっていく時代には、ローカリティという要素は絶対に欠かせない。そこで大切だと思っているのがヘリテージ。モノの歴史であったり、場所の風土や文化、人々の暮らし、また木や土といった土着素材であったりを意味しますね。それらを学び、活かすことが非常に重要だと思っています。

それから僕はローカリティの突出を非常に面白い現象だと思っています。京都はローカリティの極北のような街で、英語が通じない、英語の標識すらないお店に世界中から人が殺到している。僕も旅行が好きで、世界中いろいろな土地を訪れましたが、やはり感動するのはどこにでもある均一化した都市ではなく、思いっきり風土を感じるような、ローカリティあふれるところ。それは建築であってもモノであっても、音楽、食べ物でも同じ。その土地の文化全般をローカリティに根差して考えていくことで、より強いもの、個性的なもの、魅力的なものができるのだと思います。

ローカルの素材と先端技術を組み合わせた新しいものづくり
——そのローカリティをテクノロジーと融合させるとは、具体的にどのようなことですか? また、これまでセラミック、木などでローカリティを生かしたものづくりをされてきたようですが、現在注目されている素材や工芸はありますか?
近年、3Dプリンティング技術に着目しています。以前は3Dプリンターといえば、使える材料はもっぱらプラスチックでしたが、最近では出力する素材を自由に作ったりとカスタマイズ可能に。たとえば間伐材を粉砕して粉状にしたものを樹脂と混ぜた材料は、約80%木材が混入しているため、ほぼ木をプリントしているような状態になるんですよ。
同様にコンクリートも3Dプリントできるようになってきたので、現地の土を使って建築そのものをプリントすることができる。プロダクトも現地の木や土を混合して、全く新しい本当に独自のローカルな素材を作ることができます。今そういう研究をいろいろと進めているところです。これが、ローカリティとテクノロジーの融合ということです。
工芸と素材については、常に日本全国を訪ね歩いて探していますが、今は土、紙、竹が改めて面白いなと思っていて、最近はシルクにも着目していますね。
——テキスタイルですか?
そうですね、シルクの繊維そのものを立体的に形作る技術を今考えています。天然素材としてのシルクは、やはり儚(はかな)さ、朽ちる弱さがあるので、現代のケミカル技術を組み合わせることによって、自然素材をきちんと50年、100年使えるものにできないかと思っています。たとえば漆のお椀は、木地に漆を塗ることで100年、200年、300年と残っていく。そういったものをもう一度ローカルの素材と最新の先端的な材料、技術を組み合わせて、新しいものづくりの技法とか素材を作れないかと思っています。
職人の手仕事は絶対になくならない、なくしてはいけない
——鈴木さんのお話は、職人の手仕事を大切にするかつての柳宗悦の民藝運動を彷彿とさせます。今おっしゃった新しいテクノロジーを使ったものづくりは、職人の手仕事を必要としなくなるような気もしますが…。
それはよく指摘されることですが、逆に絶対に必要でなくならないものだと思っています。3Dプリンターもそうですが、先端技術で作られるものは日常の中で使うというリアリティがどうしてもありません。3Dプリンターは基本的にモノマテリアル、つまり単一素材で作るのが前提ですから、できたものは当然非常に均一で個性がない。
しかし、漆器を例にしてみましょう。植林し伐採し乾燥させた木をくりぬいてお椀の原形、素地を作っていた時代と比べると、3Dプリンティング技術を使えばその工程ははるかに素早くかつ正確に、また安全で効率的に恒久的な強度をもった木地を瞬時に作ることができる。木を育て素地までにする工程も非常に大切ですばらしいのですが、漆工芸の主役は、塗りの技術や蒔絵や沈金といった加飾の技術であったはず。そこまでのプロセスを簡略化できれば、手仕事の時間は格段に増やすことができます。

しかし、手仕事というのはどこまでいっても不均一ですが、その不均一さこそが豊かさでもあります。そういった豊かさとは、ディープラーニングとかAIや3Dプリンティング、コンピュテーショナルデザインではたどり着けない、人間の手だからこそ生み出せる非常に繊細で温かいもの。そこは絶対になくならないし、なくしてはいけないと思っています。
――
さて、鈴木氏はコロナ禍の中、都内のヴィンテージマンションに引っ越している。ご自身と同い年くらいの築年数だが、適切にメンテされた美しいマンションで、全方向に開口部がある開放的な住居兼ワークスペースとのこと。入居にあたってリノベーションしたそうだが、もともと状態が良かったため、床、壁をデザインして、水回りを新しくするくらいの改修だったという。
豊かな空間には住まい手の美意識がきちんと反映されている
——引っ越しされて、何が変わりましたか?
コロナ禍になっても多忙さにはあまり変わりがないのですが、リモートワークの影響もあり、今のマンションに引っ越してからは、朝日が差し込んでくると目が覚め、暗くなると寝るという、自然に寄り添ったとても健康的な生活になりました。自然のバイオリズムに合わせて暮らし、仕事ができる場所は本当にいいなと実感しているところです。ちなみにそのマンションは高台にあって周囲も閑静な住宅街なので、夜になると東京とは思えないほど真っ暗になります。
——リノベーションにあたって、デザイナーとして何を一番大切にされましたか?
僕はジェフリー・バワという建築家が大好きで、ある時期スリランカに年に3回くらい通ってバワの造った建築を全部訪ね歩いたことがあります。そのなかのひとつに「ルヌガンガ」という週末住宅があって、湖畔の小さな家なのですが、それを見たときとても感動しました。自然と融合して暮らすことがいかに気持ちいいものかと。

今回の引っ越し・リノベーションにあたっても、ジェフリー・バワの建築が頭の中にあって、光を美しく室内に取り入れるようカーテンやいろいろなものをじっくり選定しました。
また、大きめのルーフバルコニーが2つあるのですが、そこに日本各地からいろいろな樹木を集めて、四季折々の花や紅葉を楽しめるようにしようと考えています。訪ねてきてくれる仕事仲間や友人とともに、自然を常に身近に感じられるような場所をめざしています。
室内には制作された年代を問わず、自分の好きなものをいろいろ置いているので、過去なのか現代なのかよくわからないような空間ですね。なかには祖父から受け継いだ骨董や東アジアの民藝品などもあります。
——鈴木さんにとって豊かな暮らし、あるいは暮らしの中の豊かさとはどのようなものでしょうか?
ジェフリー・バワの建築もそうですが、住まい手の美意識がきちんと反映されていると、とても安心しますし、美しい、豊かな空間だなと思いますね。
それから、人は自然現象を完全にコントールすることはできませんが、光がどのように空間に入ってくるか、風はどう抜けていくかは、工夫してある程度制御することができます。僕はそうやって得られる人間本来のプリミティブな心地よさを、もう一度取り戻したい。心地よさも豊かさのひとつなのだと思います。
――
デザインの最近の流れを振り返ってみると、マーケティング、その後はブランディングのブームがあって、結局前世紀型の競争と差別化の原理から一歩も脱しておらず、デザインの本質から乖離したままなのではないか。アフターコロナに新しい社会、新しいスタンダードの誕生を期待するという鈴木氏にとって、デザインとは本来、人がシンプルに美しさ、心地よさを感じることができるモノと環境を作ることだという。自分自身に真摯に向き合い、実直に人と自然の豊かさを追求する氏の今後の活動に注目したい。
profile

1982年愛知県生まれ。2006年多摩美術大学卒業。12年プロダクトデザインセンター設立。さまざまな素材を駆使した日用品から電車車両などの公共分野のデザイン、展覧会のプランニングや空間構成、また企業や研究機関と共同で行う新素材開発のディレクションまで、活動は多岐にわたる。15年「サンティティエンヌ国際デザインビエンナーレ」に「富士山グラス」が招待出品。18年には初個展となる「鈴木啓太の線:LINE by Keita Suzuki」が柳宗理記念デザイン研究所で開催。同所での柳宗理氏以外のデザイナーによる初の展覧会となった。19年車両のプロダクトデザインを担当した『相模鉄道20000系』がローレル賞受賞。2015年〜17年、グッドデザイン賞最年少審査委員。
▶︎https://productdesigncenter.jp/