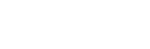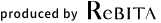今回のインタビューは、実は宮前さんからのお声がけで実現した。以前からイッセイ ミヤケの活動をいかに広く正確に伝えるか模索してきたという宮前さん。ある時たまたまR100 TOKYOのウェブマガジン「Curiosity」が目に留まり、コンテンツに見られる取材対象の幅広さと選択眼、時代の流れを見据えた視点に共感されたといい、編集部に連絡が入った。リモートで意見交換するうちに、さらに相互理解が深まり、今回の取材はリビタ・R100 TOKYOのチームスタッフも参加して、取材というよりもトークセッションのような展開となった。
——「Curiosity」を見つけていただき、ありがとうございます(笑)、スタッフ一同大変嬉しく、また光栄に思っています。
こちらこそ。僕たちイッセイ ミヤケは、ファッションとか建築といった、ある1つの業界にとらわれない自由な活動を標榜しているので、伝え方にいつも苦労していて、常にアンテナを張り巡らせて共感できるメディアを探しています。そこでたまたま見つけたのが「Curiosity」でした。

——私たちも不動産という業界だけにとらわれてはいけない、より視野を広く、異分野、異業種とシームレスにつながって、ユーザーとともに住まいや暮らしを作り上げていきたいと考えていますので、考え方の方向性が大変近いと感じ、お話をうかがうのを楽しみにしていました。
さて、まず宮前さんの近年の活動についてお聞きしたいのですが、今春新ブランド「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」(以下、エイポックエイブル)がスタート、最近ではそこから新プロジェクト「TYPE-I(ワン)」を発表されましたね。
2020年の10月に美術家の横尾忠則さんとプロジェクト「TADANORI YOKOO ISSEY MIYAKE」を発表しました。続けてこの春、新ブランド「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」をスタートさせました。いずれも僕がISSEY MIYAKEのデザイナーを2019-20年秋冬コレクションを最後に退任した直後から約2年近くかけて準備してきたプロジェクトです。異分野や異業種との新たな出会いから様々なプロジェクトをエイポックエイブルから発信していきたいと思っています。
衣服の純粋な表現としての「Session One」
イッセイミヤケでは、今までにない価値を創造していくために、社内でも異なる個性を尊重し合いながらモノづくりを行なっています。既成概念を打ち破るために、目の前のことに敢えて疑問符を投げかけることを日頃から心掛けていますが、作業に慣れてルーティンワークに陥ることもあります。そんなとき、三宅は様々な角度から課題や問いをチームに投げかけてきます。
とりわけ2018年に発表した「Session One(セッション ワン)」は、とても特異なプロジェクトでした。三宅から最初に投げかけられたテーマは「縄文人に会いにいく」で、商品化しない実験的なプロジェクトとして社内で密かに始動しました。それは、社の創立50年を目前にイッセイ ミヤケのモノづくりは今後どういった未来を歩むべきか、三宅からのデザインチームへの大きな問いかけでもありました。
そこには、近年アパレル業界が大きく様変わりし、さらに例えば環境問題に対する人々の意識の高まりなど、様々な局面で社会が変わってきたという背景がありました。それに対して自分たちはどういうスタンスで新たな衣服を提案していくのかを問い直す必要がありました。

——なぜ今、縄文時代だったのでしょうか。
ご存知のように縄文時代というのは1万年以上に渡って自然と共生した平和な社会が続いたと言われています。ではその豊かな時代に人々はどういった暮らしをしていたのか、その豊かさを学ぶ必要があるのではないか、彼らの生き方、考え方、さらに現代においてもし縄文人ならどういう服を作るのだろうかと想像してみることで、そこに僕たちが次へ進むべき道のヒントがあるのではないかと。
それで、社内でブランドの枠を超えて有志が集まり、それぞれが普段の仕事をしながら、いわば部活動的に集まって議論したり、縄文を扱う博物館に足を運んだりとリサーチを重ね、1年以上の歳月をかけて創作が行われました。縄文人の思想をもとに、考えるプロセス自体に普段のモノづくりでは得られないいろいろな気づきがありました。「セッション ワン」は、縄文人とのセッションでもあり、役職や部署など社内の垣根を超えたセッションでもあり、とても貴重な体験でした。
A-POCの進化をめざして
——「TADANORI YOKOO ISSEY MIYAKE」も「セッションワン」も、A-POCの進化のためのプロジェクトということでしょうか?
イッセイミヤケのモノづくりは一貫しています。A-POCが誕生したのが1998年で、20年以上経つわけですが、独自のモノづくりを継承し、発展させていくことの大切さを改めて感じています。A-POCが誕生した当初は無縫製ニットが代表的なアイテムでしたが、その後はプログラム技術を駆使した織物の表現が飛躍的に発達しました。コツコツ積み重ねた経験は必ず力となり、独自のノウハウとなります。そして次への可能性に発展します。
しかし、同じ枠の中だけに留まっていたら新しい発想は生まれ難くなります。新たなイノベーションを起こすためには、時には違う原動力や刺激、外からの新しい風も必要となります。「TADANORI YOKOO ISSEY MIYAKE」も「セッションワン」も既存のチームが変化し、A-POCをさらに進化させるためには必要不可欠なプロジェクトでした。


僕は横尾さんとは歳が離れていますが、三宅としては世代を超えたコミュニケーションから何か新しいものが生まれるのではないか、僕たちが変わるのではないかと考えたと思いますし、そういうチャンスをもらったのだと思います。取り組み始めたのは「セッション ワン」とほぼ同じ時期で、最初は商品化を前提とせずに、純粋にクリエーションとして取り組むところからのスタートでした。
——TADANORI YOKOO ISSEY MIYAKEは、コロナ禍真っ只中の発表となりましたが……
プロジェクトの制作中に、突如世の中がコロナ禍によって一変しました。一時は発表どころではない雰囲気となり、足踏みしていた時期もありました。しかし、アートやデザインは本来人々の生活や心を豊かにするものであって、こういう困難な時こそ必要とされるべきものだと、いろいろ悩んだ末に発表を決断しました。

——それがエイポックエイブルという新ブランドにつながっていくわけですね。
A-POCによるモノづくりは、点から線へ、線から面へと拡張し続けてきました。「点」はチームの仕事、「線」はあらゆる方向にのびるコミュニケーション、「面」は人々の繋がりによって生まれるプラットフォーム。新たな繋がりによって創造は無限に広がります。チームと共に様々な問いを立てながら、あらゆる境界を越えて、縦横無尽に駆け巡り、次の時代の衣服を探求し現実化=ABLEしていきたいというビジョンがあります。
——宮前さんは2001年に三宅デザイン事務所に入社されてすぐにA-POCに参加され、5年間活動されたということですから、思い入れも強いのでは?
そうですね、最初に配属されたA-POCでの経験がなかったら、僕は今頃全然違うデザイナーになっていたと思います。幼い頃からモノづくりが好きで、その延長で自分の服を独学で作るようになり、専門知識を高めるために服飾の専門学校に通ったのですが、徐々に従来の服づくりに対して疑問を抱くようになりました。
それまで見えなかった景色が見えた瞬間
卒業を迎えた1998年は、アップルのスティーブ・ジョブスがiMacを発表し、一般家庭にインターネットやパソコンが普及し始めた年でした。ファッションの世界ではSPA(製造小売)の隆盛が話題になるなど、時代の大きな変化を肌で感じていましたが、自分に何ができるか悩み続けていました。
そんなときにA-POCの発表を見て、本当に衝撃を受けました。当時、テクノロジーの力で世界が変わるとは感じていましたが、A-POCはさらに着る人が服作りに参加するという、従来のファッションとはまったく異なる概念、価値観を見せつけた。僕がやりたかったことは、まさにこういうことだと。ニューヨークで一年過ごしたあと、三宅デザイン事務所に入社し、A-POCの企画チームに参加できたのは幸運でした。
——入社後A-POCで活動された5年間はどんな時間でしたか?
色や形などの意匠を提案するだけがデザインの仕事ではないことに気づき、最初はとても苦労しました。A-POCのモノづくりは、糸の設計から始まり、編み、織り、染色の技術までデザイナーがかかわっていく。さらに産地に赴くことで、地域の伝統、文化、歴史が見えてきて、より素材への理解が深まる。すると、それまで見えなかった景色が見え始め、服づくりを通じて社会との繋がりを感じるようになり仕事が面白くなりました。
つまり、デザイナーの仕事は机の前に座っていても何も生まれない。様々な課題を現場で見つけ出し、そこからどれだけ掘り下げ、徹底的に考え、行動に移せるかということがモノづくりを進めていく上でとても重要な分かれ道になってくる。A-POCの仕事を通じて、デザインとは何かということを入社してすぐに三宅の側で学べたことはとても大きいです。

A-POCをさらに拡張するためのプラットフォームを作る
——モノづくりのスタンスについて、今回のエイポックエイブルでは「異分野、異業種との出会いから次代の衣服を探求、実現する」とおっしゃっています。宮前さんがお考えのコラボレーションとはどういったものでしょうか?
コラボレーションという言葉には、ブランド間の商業的なプロモーションといったイメージがあるかもしれません。僕たちの仕事は、コラボレーションというより協業という言葉の方がしっくりくると思っています。異分野のエキスパートとの出会い、ジャンルの垣根を越えたコミュニケーションから予期せぬ発想が生まれる。そこからA-POCの可能性をさらに拡張させていきたいと考えています。まずは自由な発想の場となるプラットフォームをこれから作っていきたいと思っています。
——そういった出会いは、宮前さんの方から情報収集して会いに行く感じですか?
出会いは様々ですね。この人のことをもっと知りたいと思ったら、自分から積極的に会いにいったりもしますが、偶然の出会いをとても大切にしています。例えば「TYPE-I」は、異分野、異業種とのコミュニケーションから生まれたエイポックエイブル初のプロジェクトですが、ソニーグループのクリエイティブセンターのデザイナー、北原隆幸さんとの出会いがきっかけでした。
雑誌の対談で初めてお会いしたのですが、すぐに意気投合。モノづくりの姿勢が同じで、今は協業なくして新しいものは作れないという考え方にも共感しました。そこからソニーグループが開発した新素材(トリポーラス)を使って、エイポックエイブルが関わることでこの素材の新たな価値を見出そうと、2年前から取り組んだプロジェクトでした。

——お話をお聞きしていると、衣服のデザインと同時にプロセスをデザインする、いわばファッションエンジニアリングといった印象を受けます。
A-POCの仕事ではエンジニアリングという言葉を敢えて使っています。デザインと技術を繋ぐのがエンジニアリングです。高度な専門技術を実用化することを前提に、生活のなかで役立ち、いかに美しいプロダクトを生み出せるかという能力がA-POCの仕事では求められます。全員が糸の原料選びから始まる服づくりのあらゆるプロセスに関与するため、デザイナーやパターンナーといった従来の役割分担をしないチーム構成で服づくりを行なっています。多角的な視点と複合的に解決する力が必要なので、今僕のいるチームはエンジニアリングチームと呼んでいます。
エイポックエイブルはモノづくりのプロセスを見つめ直し、作り手と受け手とのコミュニケーションを広げ、未来を織り成すブランドです。そもそもデザインとは、相手があって相手に届けるまでが仕事です。当然ながらデザイナーの役割は外観を作ることだけではありません。新たなプロセスやコミュニケーションを通じて新しい価値をどう世の中に生み出すかが問われています。

オンとオフに区切りをつけない生活
——さて、宮前さんのワークライフバランスについてお聞かせください。
仕事と生活、オンとオフは分けて考える方も世の中には多いと思いますが、僕の意識にあまりそういう区切りはありません。切り替えることが時には必要なときもありますが、アイデアを考えたり発想したりするのは仕事の時だけに限らないですよね。要するにアイデアは時も場所も関係なく、思いつくときは思いつくし、机にかじりついても出ない時は出ない。オフィスにいれば当然仕事モードですが、家にいても仕事場でも、意識としてはあまり区切りたくないというか、常にオープンマインドな状態でいられるよう心がけています。ですから、仕事中より生活の中で気づいた何気ないことがアイデアに生かされることが多い気もします。
例えばエイポックエイブルのTYPE-Uは、日常生活の中から生まれたアイデアのひとつです。昨年の春に初めてリモートワークを経験したのですが、そこにはいろいろな発見がありました。本来リラックスした格好で過ごしたい生活空間で仕事モードに切り替えるのはなかなか難しい。パジャマのようなスウェットで仕事する訳にもいかないし、かといって家でずっとジャケットを着ているのは堅苦しい。
そこで考えたのがシャツのような柔らかい着心地のジャケットです。特徴のひとつは、着る人が自由に形を変えることができる独自の“形状記憶素材”を使っていることです。例えば、袖口を捲り上げても袖が落ちてこないので作業する時の煩わしさもなければ、気分に合わせて服の表情を自由にアレンジできる。これは新たな生活様式の中で、「こんな服があったらいいな」と僕自身が着たいと思う服を考えついた一例です。

——宮前さんにとっての「豊かさ」とはなんでしょう。
僕はオフィスまで毎日電車で通っていて、街ゆく人を眺めたりするのが好きです。その日常の中の小さな気づきや違和感がクリエーションにつながる源泉だったりもします。僕自身、ごく普通の環境に身を置き、生活のリアリティをいつも感じていたいという思いがあり、週末にパンを焼くとか、庭で野菜を育ててみるとか、そうやって何気ない1つひとつに向き合う時間ができることが、自分にとっての豊かさなのかなと最近思います。僕たちの仕事が誰かの生活の一部になることが喜びで、これからもデザインを通じて心の豊かさを創造していきたいと思っています。
profile

1976年東京都生まれ。2001年三宅デザイン事務所に入社し、三宅一生と藤原大が率いたA-POCの企画チームに参加。その後ISSEY MIYAKEの企画チームに加わり、2011年から19年までISSEY MIYAKEのデザイナーを務めた。2020年秋「TADANORI YOKOO ISSEY MIYAKE」を発表。新ブランド「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」では、エキスパートを集めたチームを率いて、A-POC の更なる研究開発に取り組む。
Profile photo:Takeshi Miyamoto
ISSEY MIYAKE INC.
▶︎https://www.isseymiyake.com