事業家としての遠山氏と、ヒルサイドテラスの存在

現在、遠山正道氏が代表を務める「スマイルズ」は、社内ベンチャーの成功例として必ず取り上げられる。安定した大企業から飛び出して新たな挑戦を決断したきっかけは、氏が学生時代から描いていたという絵の個展だった。そしてその会場となったのが、氏が偏愛してやまない代官山「ヒルサイドテラス」だという。
実業家として、アーティストとして、いわばボーダレスに活動するきっかけとなった場所、ヒルサイドテラス。その存在は氏のビジネスやコミュニティ論、アート思考にも少なからずリンクしているように思える。そこで、まずは遠山氏の手掛ける事業とビジネス論について話をうかがった。
「アーティスト」と「キュレーター」の2つの顔を持つ
遠山氏曰く、スマイルズの事業の柱は2つある。その1つは「自分事業」だという。
自分事業とは、常に“自分ごと”として自分の中に“根拠”があるもの……、例えば好きなもの、やりたいことを世の中に提案していくというもの。“食べるスープ” 「Soup Stock Tokyo」も、ネクタイブランド「giraffe」もそうやって生まれた。それは組織としてだけでなく、社員一人ひとりにも求められる。
もう1つの柱は、この自分事業のノウハウを、必要とする企業や団体などにアドバイスする「コンサルティング業」。遠山氏曰く、それは「自分はいったい何がしたいのか?」を絶えず問い続ける作業で、クライアントの業種、業態も実に多彩。企業はもちろん、自治体や、最近では魚市場からも問い合わせがあったそう。
そうして「何がしたいのか?」が見つかれば、デザインまで含めて具体化し事業化へと導く。

この2つ目の柱「コンサルティング業」について、遠山氏はアートの世界でいうキュレーションに似ているという。キュレーターは自分で何かを作るわけではないが、与えられた空間、例えば美術館やギャラリーで、この場所で何を提案するか考えながらアーティストをピックアップし、場合によってはアーティストに指示を出しながら、作品を作り上げていく。
コンサルティングもこれに似たようなところがあり、企業をアーティストだとすると、その個性や強みを引き出すキュレーターの役割を果たしている、と考えている。
「何かを生み出すアーティスト側の立場と、アーティストの強みを引き出すキュレーター側の立場。その両方からアプローチするのが、私たちスマイルズです」

ところで、遠山氏自身、絵を描くアーティストでもある。その対極にあるビジネスとは、どのように折り合いをつけているのだろうか?
「私にとってはほとんど同じですし、同じにしていきたいと思っています。視点をずらせば、それは経済と文化の話になるのですが、私はその“2項軸”を常に持ち続けたいと考えています」
氏によると、企業も「法人」と呼ばれるように、一個の人格をもつ存在であり、個人と同様に社会的責任がある。経済のみでなく、文化にも目を向けるべきだという。
実際、スマイルズは「法人」という作家として、これまでに芸術祭に何度か参加している。経済と文化、2つの軸を両輪に邁進する遠山氏は、“経済の人”と話すときは文化的な立ち位置を取り、“文化の人”に対してはビジネスマンの顔つきになるそうだ。
ビジネスとアート、経済と文化……両極にあるべきものが調和し一つの思考に昇華しているように感じる、スマイルズの事業。それはある意味、商業施設でありつつ上質なアートやカルチャーを発信し続けているヒルサイドテラスの存在と通じているようにも思えた。
運命を変えた、ヒルサイドテラスでの個展
少し話を戻そう。遠山氏のユニークな活動の端緒を開くことになった、自身の絵の個展。それは大手商社に入社して10年目、将来を見据えて「自分はいったい何がしたいのか?」という疑問に対する回答だった。この個展の体験がSoup Stock Tokyoの立ち上げにつながったという。そして、その会場となったヒルサイドテラスは、氏の住まいでもあり、個展の開催はここに住みはじめて3年目のことだった。
ヒルサイドテラスと遠山氏の出会いは、巡り合うべくして巡り合った運命的なものだった。まず、ヒルサイドテラスの開発プロジェクトを一任された世界的建築家・槇文彦氏と遠山氏は、縁戚の間柄。遠山氏にとって槇氏は、親戚のなかでもとびきり“素敵なおじさま”で、子どもの頃からあこがれの存在だったという。
次に、よく知られているように、ヒルサイドテラスはオーナーの朝倉家(朝倉不動産)と槇氏が30年という長きにわたって造り上げ、育ててきた複合施設でありコミュニティだ。その朝倉家には、慶應の幼稚舎からなんと就職先の大手企業までずっと一緒だったという同期の仲間がいた。

当時、ヒルサイドテラスに住むのは、遠山氏にとっても夢のまた夢だった。第6期の竣工日が遠山氏の結婚式と2日違いだったこともあって、ダメ元でその同期の彼に聞いてみたところ、たまたまファミリー用に用意された1室が空いていた。偶然と幸運が重なって入居となり、以来現在に至るまで、約30年近く住み続けている。
「ヒルサイドテラスは不思議な場所です」と遠山氏は語る。空き室が出てもテナント募集を積極的に行わない。オーナーとの相性が大切にされ、合わなければ空室も致し方なしの姿勢。言ってみれば、欲がない。F棟にあるヒルサイドカフェもそうで、奥まった立地からか平時から空いていることが多いカフェだが、立て看板を置いたりして集客に努めるようなことはしない。
槇氏は著書のなかでも「都市における孤独」について言及しているが、ここは都市空間にありながら、ひとり静かにサンドイッチと紅茶をいただくことの豊かさを考えさせられる場所だという。もちろん経済活動として見れば大変だが、大事にしている価値の優先順位として、単なる経済を上位に置かないという姿勢がうかがえる。

その遠山氏がヒルサイドテラスのなかで好きな場所として挙げたのが、階段室とエレベータホールだ。朝、4階の住居から出かけるとき、大抵は階段を使うそうだが、そのときの階段室を満たす光がなんとも言えず心地いいそうだ。
「何か、天国から“合理的に”地上へ降りていくような感じがあって、とても好きな時間です」
“合理的”というのは「モダニズム建築の合理的な機能として階段があるからで、雲の上の天国から、ふわりと降り立つのではなく、階段をちゃんと足を使って降りていく」からだと遠山氏は語る。

また、1階のエレベータホールには、白い壁に囲まれた空間にグレーの面があり、それは一見、影のようでもある。「設計時の意図はわからないが、まさに陰のようなコントラストがあらかじめ設計されているように思える」という。
稀有のコミュニティ、理想のアーバンビレッジ
2019年、第一期竣工から50年を迎えたヒルサイドテラスは記念行事を開催、遠山氏も含め、ゆかりのある50人の寄稿をまとめた書籍『HILLSIDE TERRACE 1969-2019』(槇文彦、北川フラム著、ヒルサイドテラス50周年実行委員会監修)も出版された。
実に半世紀という長い時間のなかで、常時メンテナンスを入れたにせよ経年劣化など物理的な変化はあっただろう。ただ、その本質はまったく変わっていないと遠山氏は断言する。オーナー、住民、テナントが一体となって作り、守ってきた理想のアーバンビレッジ(都市の中の村)の文化的価値は、高まりこそすれ劣化することなどなかった。
そもそも、代官山の旧山手通り沿い一帯がこれだけ優れた環境を維持できたのは、ヒルサイドテラスがあったからだ。例えば、計画当初は高さ規制が10mだったが、後期になると用途地域も変更となり高さも容積率も緩和された。しかし、槇氏は通りに面したところは常に10mに抑えて景観を守った。電柱も地中埋設にしてあるから空が広い。
「きっと、ディベロッパーとして朝倉不動産がいろいろ行政と調整しながら進めたと思いますが、そういったパッと見には気づかない、ある種の引き算が素晴らしいですね」
最近の大きな変化は、鎗ヶ崎の歩道橋がなくなったこと。これも都市景観としてのヒルサイドテラスの価値をさらに高めている。
新たなコミュニティ「新種のimmigrations」をヒルサイドテラスから発信
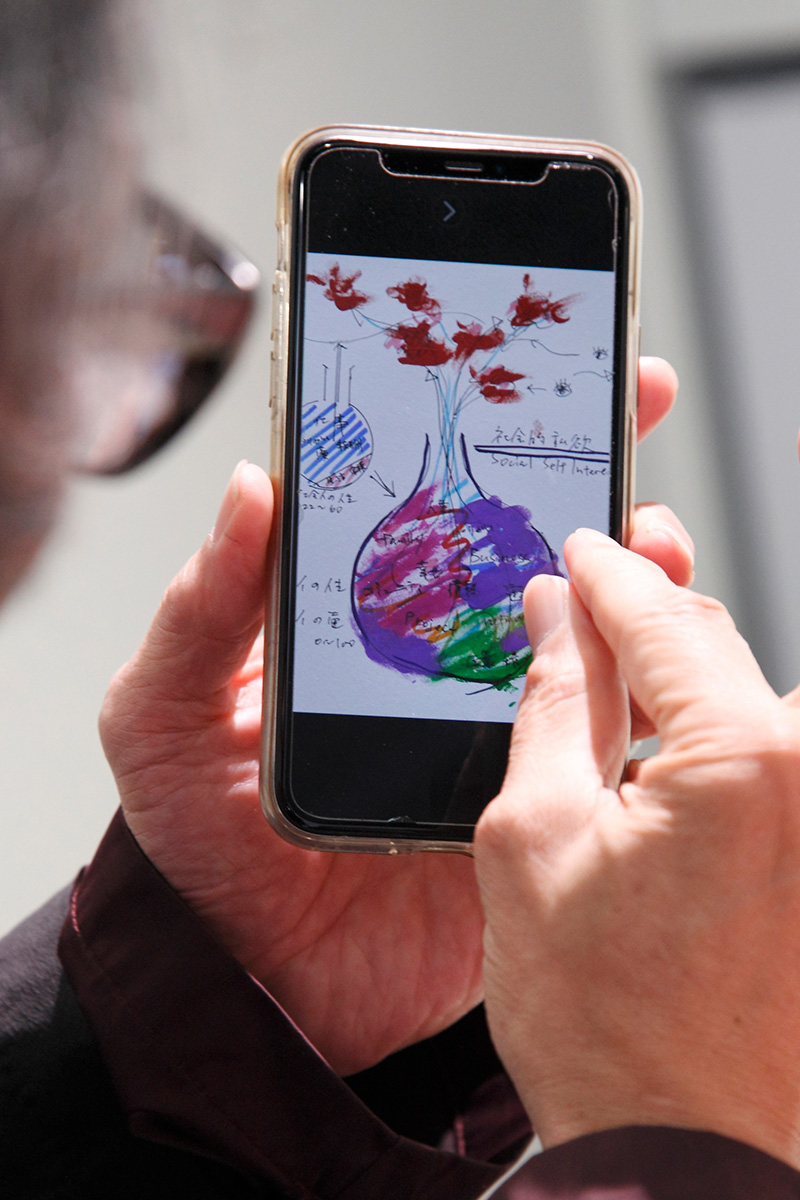
「新種のimmigrations」https://immgr.site
さて、昨年(2020年)遠山氏は「新種のimmigrations」(通称イミグレ)という新たなコミュニティを立ち上げた。まるで小さな国のようなコミュニティで、「住民(会員)は入国審査を経て入国、住民税(会費)を払って参加する。その半分は経費、半分は住民の幸せの拡充のインフラとして再分配される」という。
企業と違ってミッションはない。ただいるだけでいい。何が起こるかわからないし、何も生み出さなくてもいいが、そこからビジネスが生まれるかもしれない。その会員が自由に利用できる小さなスペースを、ヒルサイドテラスに設けている。

きっかけはコロナ禍だ。その影響は各方面に甚大な被害を与えており、スマイルズも例外ではない。ただ、そういった不安や苦境のなかにあって、遠山氏はむしろ落ち着きを取り戻した感じがしたという。
例えば、自分で料理を作り、家族で食卓を囲んで食べていたりすると、幸せは意外と足元にあった、と感じる。そのとき自問したのは「自分が自分の幸せを担保できているか」だ。遠山氏はこれを「1分の1の人生」と言っていて、同じ価値観を共有できる仲間が集まれば、誰もが穏やかで平和なコミュニティができるのではないかと考えた。
遠山氏は2018年、谷川俊太郎氏の詩を基に建築家・篠原一男が設計した北軽井沢のTanikawa Houseを取得している。現在、イミグレのメンバーとも、その周辺地域での活動なども検討している。

「もし私がここではなく別の場所に暮らしていたら、全然違う人生になっていたと思います。あのときの個展もここで開催されることもなく、よってSoup Stock Tokyoもなかったと思います。それがいいか悪いかはわかりませんが、とにかくヒルサイドテラスが私の人生を引き上げてくれているというのはすごく実感としてありますね」と、遠山氏は述懐する。出会いは幸運な偶然であったのかもしれないが、運命は必然だったのだろう。
最後に、どういうとき、どういった場所で豊かさを感じますか? という質問に、遠山氏は次のように答えた。
「人と光ですかね。ここで共に暮らす人たちとの触れ合いや集い、先ほどの階段室の光や、通りやパティオの木漏れ日。それは住宅の中にも回り込んできて、光と影が風に揺れたりする様は都市であることを忘れさせてくれる。そういうときに確かな豊かさを感じますね」

profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年新種のコミュニティimmigrationsを立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。
▶︎http://www.smiles.co.jp/
▶︎http://toyama.smiles.co.jp
取材協力
代官山ヒルサイドテラス
▶︎http://hillsideterrace.com/


















