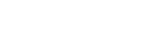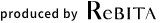シューマンの音色で目が覚め
ある年の夏、パリ左岸に位置する、カルチェ・ラタンの小さなホテルに滞在し、ひとりで過ごした。
こぢんまりした部屋と、窓から望むリュクサンブール公園の豊かな緑が一目で気に入って、何度も泊まるようになった宿だった。
朝起きて窓辺に置いた椅子に座ると、パリの青い空と新緑の景色が目前に広がり、いつまでも目を奪われた。オレンジジュースをグラスに注ぎ、近所のカフェで買った甘いサブレをひとくちかじった。耳を澄ますとどこかからピアノの音色がかすかに聴こえる。決して上手とは言えないが、シューマンが作曲した子どものための小品だった。こんな小さなしあわせによろこぶ朝がパリにはあった。

数日前、友人に連れていってもらったオベルカンフのブロカント(骨董屋)で見つけたギターケースのことが気になって仕方がなかった。ギターケースは小ぶりで、そのかたちからして古いアメリカのものだった。店主に訊くと、「ああ、これはある客から預かっているものだから売り物ではないんだ」と言い、「戦前のマーティンだ。アメリカの」とつぶやいた。フランス人は、服でも食べ物でもフランス製のものを好むところがある。「アメリカの」という言葉がそれを物語っていた。
ふと思い立ち、ぼくはブロカントをもう一度訪れた。木枠の古いドアを開けようとすると鍵がかかっていた。中を覗くと店主ともうひとり誰かいるのが見えた。ぼくに気がついた店主はドアの鍵を開けて「今日は休みなんです」と言った。「先日見たギターケースが気になって来たんです」と言うと、「ああ、ちょうどその持ち主が今、来ているんですよ」と店主は笑って答えた。そして「それならギターも見てはいかがですか」と店の中にぼくを入れてくれた。
アメリカからパリに渡ったギター
古いソファの上にギターケースは置かれていた。「こちらが持ち主です」と言って店主はひとりの女性をぼくに紹介してくれた。女性はぼくに英語であいさつをしてくれた。女性はアメリカ人で、名前はたしかキリアンと言った。「彼はあなたのギターが気になっているようですよ」と店主が言うと、「これは亡くなった祖父がアメリカで手に入れたもので、パリに移住したときに持ってきたものなんです」と女性は古ぼけたケースを静かに開けて、ギターを取り出してくれた。
ギターを見てぼくは息を呑んだ。それはマーティン社が戦前に作った小ぶりなアコースティックギターで、ところどころに貝の装飾がされた0-45という希少なモデルだった。ギターと一緒に購入時の保証書があり、1927年11月2日にニューヨークの楽器店で購入した記録があった。
「見てわかるようにネックが折れてしまっていて使えないのでどうしようかと思って」と女性は言った。店主は「こちらで買い取っても、こんな状態だと値段はつけられない」と言った。
マーティン0-45ギターは、フォークシンガーのジョーン・バエズといった、数々のミュージシャンに愛されたギターとして知られている。この年の生産数は19本のみで、希少なローズウッドを使い、戦前の腕の良い職人が手がけたものだ。このアコースティックギターの美しい音色は伝説とまで言われている。
こんな奇跡のような偶然があるのかとぼくは驚いた。なぜならマーティン0-45ギターは、ぼくが何年もかけて探していた憧れのギターだったからだ。
まるで映画のような筋書き
「もしよかったらぼくに引き取らせてくれませんか。もちろん値段はあなたが決めてくれて結構です」と恐る恐る言うと、「あなたがこのギターをしっかりと修理して、大切に弾いてくれるならよろこんでお譲りしますよ」と女性は言い、店主に目配せをすると、店主は静かにうんうんとうなずいた。女性はギターをケースにしまい、近所のカフェに行きましょうとぼくを誘った。
女性の祖父は60代になってからパリの18区のアパルトマンを購入し、およそ20年間、パリでひとり暮らしをしていた。職業は作家で、パリでの暮らしを描いたエッセイを書いて生計を立てていた。なじみのカフェで週末の夜になるとBGM代わりにギターを弾くのが楽しみだった。そんな祖父が「ミニヨン(かわいらしい)」と呼んで愛したギターだが、あるときの不注意でネックを折ってしまい、それからギターは弾かれることなく遺されたということだった。
「さっきはあなたに譲ると言ったけれど、まずはあなたに預けるのでネックを修理してください。修理をしたらあなたのギター演奏をわたしに聴かせてください。値段はそのときに決めますので」と女性はそう言って連絡先を書いたナプキンをぼくに渡し、ギターを置いたままカフェを出ていった。この出会いというか、こんな映画のような出来事があるのかと、ぼくは呆然となって、しばらくカフェの椅子から立ち上がれなかった。
そんなふうにしてぼくの手にやってきたギターだが、戦前のマーティンギターを修理しようとする職人はパリには皆無で、苦労しながらパリ中を探し歩き、やっとのことでギター専門ではないが、ネックの修理ができる年老いた楽器職人を見つけることができた。しかし、最低でも修理に1年はかかると言われてしまい、ぼくは困り果てた。
女性に連絡をし、1年以上かかることを伝えると、「すてき。わたしはあなたがギターを持って現れるのを1年でも2年でも待つわ。なんてしあわせなんでしょう。あのギターの音色が聴けるなら何年でも待てる」とうれしそうな声で言った。
「何年でも待てる」という言葉がぼくの胸にいつまでも残った。なぜなら、ぼくにとって何年でも待てることってあるだろうかと思ったからだ。そして「待つ」ということが、彼女にとっては、すてきなことであり、しあわせであるというその捉え方に、はっとしたのだ。

季節はめぐり、私たちは待つ
待つとは、何かを信じること。
たとえば、季節がめぐるのを信じて土に種をまくように。会いたい人が来てくれると信じて胸をととのえるように。
そう、待つことには、どこか不安や焦りが静かにつきまとうけれども、ふと立ち止まってみると、その静けさの中に確かなしあわせがあることに気づくのだ。そしてまた、それがどんな理由であれ、自分を待っている人がいるということは、誰かの心に自分という存在が灯っているということのしあわせがある。
待つことと待たれること。それはおたがいの存在を信じあう、言葉のない静かな祈りのよう。今、そんな毎日をうれしいと思う自分がいる。
季節はめぐって春から夏になり、先日、あと少しでギターの修理が終わるとパリから連絡があった。
もう一度パリを訪れる理由があることのしあわせをぼくは抱きしめている。フランス語に「ダン・レ・ジュール・キ・ヴィエンヌ(近いうちに)」という言葉がある。彼女がぼくと別れるときに言ったフランス人がよく使う言葉だ。この言葉をなんだかとても気に入っている。

profile

エッセイスト。クリエィティブディレクター。「暮しの手帖」編集長を経て、「正直、親切、笑顔」を信条とし、暮らしや仕事における、楽しさや豊かさ、学びについての執筆や活動を続ける。著書に『今日もていねいに。』(PHP研究所)、『しごとのきほん くらしのきほん100』(マガジンハウス)、『正直、親切、笑顔』(光文社)など多数。