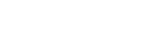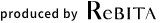抽象的な言葉よりも、リアルなものづくりを
ハタノワタルは学生時代、東京の多摩美術大学で油絵を専攻していた。現代において絵画を学ぶことは、描くという技術を磨く以上に、その核になるコンセプトの探究であるのは言うまでもない。こうしたアートに打ち込むなかで、ハタノさんは自分ならではの表現を求め、和紙を画材にすることにした。
「ある抽象的な概念によって作品をつくることをメインにしているうちに、もっと作品の内側に入ったところからものを生み出したいと思うようになったんです。そのための出発点として、誰がつくったかわからないキャンバスではなく、和紙に描いてみたら、体験が全然違った。体が喜んでいる感じがしました」とハタノさんは話す。「この感覚を深掘りしていきたい」。彼はそう直感した。当時、手にした和紙は、京都府綾部市の伝統産業である黒谷和紙。最も強度のある和紙を求めて出会ったものだった。


大学を卒業し、短期間ながら東京でデザイン事務所に勤めたハタノさんは、やがて北海道で農業をしようと決心する。デザインもやはり、不特定多数の人々が買うものをつくるという意味で、彼にとっては抽象的でありリアルでないように思えた。自身が暮らす東京という都市自体も抽象的だと感じていたそうだ。
「だんだん言葉とか概念とかが嘘くさく聞こえてくるようになってきました。北海道に行ったのは、大地で作物を育てて収穫する、そんなリアリティを求めていたからです。当時はよく全国を訪ねて山登りをしていました。想像を絶するような小さな村にも人の営みがあり、昔から同じような暮らしをしているのを目にします。そんな人たちが暮らしを語るのと、美大生が暮らしを語るのとでは、歴然とした差がある。そのギャップを埋めたいと考えていました」


だからといって、ハタノさんはアートに見切りをつけたわけではない。ひとりの表現者として、よりリアリティのある働き方を選んだのだ。そして夏から秋まで北海道で農作業をしながら、冬から春にかけての仕事としたのが、学生時代に使った黒谷和紙をつくることだったという。「昔から日本では和紙づくりが冬の仕事の代表だと聞いていたので、ちょっとやってみようかな」と、最初は気軽な思いつきだったが、すぐに本格的に打ち込むようになった。
「やがて子どもが小学校に上がると、季節ごとに移動する生活はもうできないので、紙漉きを専業にしました。数年間の修業を経て、当時は僕が黒谷和紙の産地でいちばんたくさん紙を漉く職人だった。しかし和紙は値段が安いので、どうしても月15万円以上稼ぐことはできません。その限界を身をもって知ったから、自分で和紙を売るしかないと考えた。そのためには和紙の魅力を広く伝えなければいけない。自分で実験し、活用して、現代の暮らしに和紙を広める方法を見つけていったんです」


サステナブルな未来を考えると、伝統の継承に行き着く
和紙をテーマにした実験とは、それを自宅などで「使い倒す」ことだった。現在、伝統的な和紙の産地では、機械漉きを取り入れたり、樹脂などの素材に応用するなど、さまざまに新しい試みを進めている。しかしハタノさんが使うのは、古くから継承される和紙そのもの。主原料は自分たちで栽培する楮(こうぞ)で、その皮を叩きほぐし、水に入れてかき混ぜ、簀桁(すげた)を使って漉いていく。一連の作業はすべてハタノさんの工房やその周辺で行う。
「持続可能ということは大学の頃からずっと考えていて、昔からあるものを先に繋げるのがいちばんだと思うんです。新しい技術や素材を持ち込んで、その時はいいものとされても、先々どうなるかはわからない。昔からあるものを大切に守っていけば、未来も絶対あり続けます。それがうまくいくとわかれば、過疎高齢化が進む地域であっても、だんだん人が集まってくる」
―方で、古来、人々は和紙の使い方について工夫を凝らしてきた。襖、提灯、傘など、時代が進むにつれて和紙の用途は広がっていったのだ。
「それの繰り返しなんですよ。僕が和紙をアートに使うのも、工芸と組み合わせるのも、新しい用途を付け加えるということです」
ハタノさんにとって、伝統の継承はそれ自体が目的ではない。持続する未来をつくる鍵が、そこにある。こうした確信をもっているのだ。


ハタノさんは現在、和紙づくりを続けると同時に、プロダクト、インテリア、アートピースなどきわめて幅広い仕事を手がけている。いずれも自身の工房でつくる和紙を用いたものだ。彼の活動について共通するテーマのようなものを挙げるなら、永遠性や普遍性ということになる。時代を超えて誰もが「美しい」と感じるものについて、いつも思いを巡らしているという。
「クリスチャンではないのですが、教会に入ると、美しいと感じます。すべての人がその美しい教会の中でそれぞれの祈りをささげている。美しさが安心や先へ続くビジョンと繋がっていると思うのです。そんな場所をつくれないかなと思うんです。アートは場の空気をつくる装置と意識して制作し、それを収める空間も一緒につくっていきたい。来てくれた人が必ず心地よいと感じ、自分の思いに素直になれるような場所です」


好きな場所で暮らすことが、いちばんの豊かさ
綾部市にあるハタノさんのギャラリー兼アトリエでは、彼の思いをはっきりと体感できる。仕切りのない広々としたスペースに、アートワークの代表作である『積み重なったもの』をはじめとする作品を常設。壁面など内装全体に和紙をふんだんに用いてあり、その心地よい奥深さが訪れた人を包み込む。特に印象的なのが、天井にある四角い「闇」だ。
「この空間は最初に闇から発想していったんです。昔は夜になれば外は闇だし、家の中にも暗い屋根裏があり、煙突があり、たくさんの闇があった。そこからいろんなところに繋がっていく感覚がありました」
現代において失われてしまった闇を、ハタノさんは自分以外の何かを感じさせるものと位置づけている。闇のない世界では、人はすべてを理解し、コントールできるものとして捉えがちだ。闇のなかには常にぼんやりと「他者」がいて、畏れの対象であるとともに見守ってくれる存在でもある。壁面の『積み重なったもの』も、闇と光が一対でディスプレイされている。


ハタノさんは日頃から、このギャラリーの一角に置いた椅子に座り、静かな時間を過ごすように心がけている。そばにある四角い窓の外は、青々とした山並み。隣接する土地には、もうすぐ庭をつくる計画がある。
「ずっと仕事で忙しくて、自分ひとりで考えごとができるのはベッドの上だけだったんですが、ここで初めて自分の場所をつりました。窓の形は正方形ではなく、自然に外が見えるように縦横のバランスを決めています。このギャラリーができて、戦国武将が自分の茶室をつくった理由がわかる気がしました(笑)。自分の見たいビジョンを空間で表現することには大きな意味がある。訪れた人も、その体験を通して発想が変わり、世界が変わっていくかもしれません」


自分、家族、地元に対して愛をもち、リアリティを大切にしながら暮らす。そんなハタノさんの生き方は、ひとりの表現者として、そして人間として、とても豊かに見える。
「自分の好きな場所で、希望が叶えられるように暮らすのが、いちばんの豊かさだと思います。仕事を引退した人が山のなかに引っ越して、お蕎麦屋さんを始めたりしますよね。たとえお客さんが来なくてもとても幸せそうで、そういうことです」
ハタノさんのギャラリー兼アトリエがある場所は、都会の基準からは信じられないほど土地や建物が安価で、その点においてはハードルが低い。決して選ばれた人だけが手に入れられる「豊かさ」ではない。
「努力とは違う気がするけれど、それを実現させる気持ち、求める力は必要でしょうね。いちばん居心地がいいと思えるところが見つかったらそこに行く、というだけの話です」
思うがままに生きると、きっと豊かさは後からついてくる。ハタノさんの言葉には、自然と誰もを勇気づけるものがある。


profile

和紙職人、工芸家、アーティスト。1971年、兵庫県淡路島生まれ。多摩美術大学絵画科油画専攻卒業。在学中に和紙と出会い、1997年、黒谷和紙の研修生となり、2000年に黒谷和紙漉き師として独立。2007年、京もの認定工芸士となり、2018年に紙漉キハタノを設立。現在は京都府綾部市を拠点に、店舗、住宅の壁や、床、家具などへの和紙の施工などを通してかつて暮らしの中で生きていた和紙の可能性を現代の暮らしに提案している。また、国内外で和紙で制作したアート作品の個展や展覧会を開催している。
▶︎https://www.hatanowataru.net