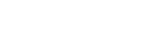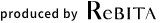坂下の老舗店と“パラパラ”聖地のディスコ跡
神楽坂で飲み食いする……なんていうと、なんとなく遊びなれたオトナの雰囲気が漂うものだ。が、最近夕刻などに訪ねると、外国人観光客とともに20代くらいの若い人がけっこう目につく。カジュアルなビストロやカフェの類いが増えてきたのも理由の一つだろうが、昭和レトロのブームなんかも多少関係しているのかもしれない。

さて、そんな神楽坂界隈を歩くわけだが、アプローチの駅としては神楽坂駅や牛込神楽坂駅より、JR飯田橋駅の西口が適当だろう。駅を出ると、外堀通りのすぐ向こうに神楽坂(早稲田)通りの坂下の入り口が見える。ここから坂上近くの毘沙門天(善國寺)門前を過ぎて、大久保通りの神楽坂上交差点あたりまでは、明治の頃から露店が並ぶメインストリートだったようだ。


坂下近くの店では左側の「田口屋」という生花店やウナギの「志満金」、右側の「不二家」(唯一、ペコちゃん焼を売っている「不二家」として有名)はかなり昔からの店で、「不二家」の隣にあった「紀の善」という甘味処の老舗は惜しくも数年前にやめてしまったが、その3~4軒先のビルにかつて“パラパラ”をブレイクさせたディスコがあった。よく見ると、いまも1階のゲームセンター上の外壁に「TWIN STAR」の看板が残されている。僕は2000年代の初頭に雑誌の取材で、このビルの2階に入っていたディスコ「TWIN STAR」にパラパラとそのギャルたちの様子を観察しに行ったことがあった。もっとも、このディスコはそれよりおよそ10年前のボディコン・ギャルたけなわの頃にオープンし、できた当初に入ったおぼえがあるけれど、何らかの事情があったのか、前身のパチンコ店で景品係をしていたとかいうオバチャンがそのまま玄関のクロークをやっていて、へーっと思った印象がある。ともかく、神楽坂でディスコ、というのはちょっと珍しかった。

名画座の記憶と石畳の路地横丁
少し坂下側にもどるが、昔の「紀の善」の脇から奥へ続く神楽小路という飲食横丁もいい。昔風のパチンコ店の看板も見えるが、やがて突きあたる軽子坂の角、取材時はサラ地になっていたけれど、ここに「ギンレイホール」と「くらら劇場」という2軒の映画館があった。ギンレイのほうは名画座で、地下の「くらら劇場」はポルノ館だったのだが、「TWIN STAR」にパラパラの取材に出向いた頃にも近い2000年代初め、ここで上映されていた映画の看板に、「くいこむ犬もも」の題名が書かれていたのが忘れられない。これは明らかに「太もも」の書きまちがいだろう。

“犬もも”の記憶が残る軽子坂を上っていくと、左手が神楽坂名所の石畳路地エリアになるわけだが、神楽坂仲通りも本多横丁の口も見送って、その先の兵庫横丁と呼ばれる路地へ入っていくのが僕の好み。道筋がちょっとクランクするところに看板が見える「和可菜」は料亭街らしい小旅館で、とりわけ文人贔屓の宿として知られたが、旅館はもう閉じてしまったと聞く。僕は一度だけ取材がてら泊めてもらったことがあったけれど、当時のエッセイを読み返すと、あの“犬もも”の看板を見つけたのはここに宿泊したときだったのだ……。

旧料亭と思しき建物を使ったフレンチやイタリアンの店が目に入る石畳の狭い路地をくねくねと進んで行くと、そのうち正面に神楽坂通りの向こうの毘沙門天が見えてくる。ここで一旦、神楽坂通りを下って、やり過ごした本多横丁から“かくれんぼ横丁”のあたりをぐるりと回ってくるのもいいけれど、文章としてはそろそろ毘沙門天にふれよう。徳川家康が江戸城北方の防衛の意をこめてここに置いたのが「善國寺」の毘沙門天――江戸の時代こそ素朴な門前町だったが、要するに神楽坂の町の原点となったお寺だ。もっとも、2007年の年頭に二宮和也主演のドラマ『拝啓、父上様』のロケで使われたのをきっかけにして、いまも境内の絵馬は一見して「嵐」の関係のものが目につく。ファンの参詣地として定着したようだ。

名建築と由緒ある町名が並ぶ屋敷町
この辺から南西側の屋敷町のほうへ進路を向けよう。いくつかの横道があるけれど、毘沙門天から坂下側へ3つ目、角にハイヒールの看板を出したシャレた靴店のある道は見番横丁と名づけられていて、入ってすぐ先の曲がり際に「東京神楽坂組合」の表札を掲げた見番(芸者さんの稽古場)のクラシックな建物がある。傍らに置かれた小さな伏見稲荷の赤い鳥居が艶っぽい趣を添えている。

道なりに進んでいくと、やがて町名は袋町、左折すると若宮町に変わり、逢坂という急な坂の脇に「東京日仏学院(アンスティチュ・フランセ東京)」の素敵な白亜の校舎が垣間見える。神楽坂にフレンチの料理店が多いのは、こういう施設も関係しているのだろう。山側に立つのが坂倉準三の設計によって1951年(昭和26年)に竣工した旧館で、1階の吹きぬけ通路の両側に絵ハガキなんかを並べた売店がある感じなどは、欧米の古いリゾート地のプチホテルを連想させる。南側はもうお堀端だから、低地にビルがない時代は対岸の九段の丘まで見渡される眺望のよい場所だったに違いない。

逢坂を下ると東京理科大学の敷地だが、そのままこの道を直進するとやがて右側は石垣になって、木立の向こうに“歴史遺産”を思わせる日本家屋が見えてくる。立派な門の傍らに警備の警官も常駐するこの家は「最高裁判所長官公邸」に使用されている「旧馬場家牛込邸」と呼ばれる屋敷。1928年(昭和3年)にこの家を建てた持ち主の馬場家は、北前船から始まる富山県本拠の海運王だから、東京の拠点のここにはわざわざ名義に「牛込」と付けたのだろう。

道を挟んだ向かいの家もスパニッシュ建築調の風情ある洋館だが、この辺は「東京日仏学院」のある市谷船河原町、「最高裁判所長官公邸」は若宮町、向かい側は市谷砂土原町、払方(はらいかた)町…と、由緒のありそうな町名が小刻みに並んでいる。さらに、南町、中町、北町、箪笥(たんす)町、岩戸町、横寺町……神楽坂周辺の牛込地区の町名は明治の頃からほぼ変わっていない。東京でも貴重な地域なのだ。
散歩のフィナーレは「赤城神社」から江戸川橋
中町の「宮城道雄記念館」の前を通りがかったら、ここは改築工事中のようで、以前の建物はガレキになっていたが、その先から地蔵坂の通りに入って神楽坂上の交差点近くに出てきた。この交差点はかつて「肴町(さかなちょう)」という市電(都電初期も)停留所があったことから、古い人はそう呼ぶ。
神楽坂散歩、大久保通りを右のほうへ行くと「筑土八幡神社」というのもあるけれど、このまま神楽坂通りを直進していくと、東西線・神楽坂駅の最も飯田橋寄りの出入り口がある「赤城神社」の参道口あたりまでは神楽坂の商店筋というイメージだ。右方に見える鳥居をくぐって「赤城神社」の境内に入る。10年ほど前に隈研吾の設計によってリニューアルされた、木とガラスを調和させた社殿や隣接するマンションも見どころの一つだが、ここに来るといつも境内裏の断崖に立って北方を眺める。

昭和30年代くらいまでは、神田川の向こうの小日向や目白台の丘まで眺望できたというこの崖際。いまはもちろんそういう景色は望めないが、社殿横の急な石段から赤城坂を下って江戸川橋まで歩いていくのが、僕の神楽坂散歩のフィナーレ。赤城坂を下って築地町、水道町に入るとあたりは印刷や紙の工場街となって、江戸川橋手前の地蔵通り商店街に差しかかると神楽坂とはまた違った空気の街にやってきた……というトリップ感が味わえる。

泉麻人のよそ見コラム

神楽坂の“シロガネーゼ”
前回、白金の話を書いたけれど、神楽坂上をちょっと北側に入ったあたりに白銀町という町がある。ここは前者のシロカネと違って読みもシロガネだから、この辺の女性こそ、真のシロガネーゼと言えるかもしれない。
実は今回の神楽坂散歩、途中でランチを食べようという心づもりで来たのが、歩いた月曜日は候補にしていた店がどこもことごとく休業なのだった(スマホでマメに調べればよかったのだが)。
どうしようか……と思っていたら、神楽坂上の交差点のところに肉まんの「五十番」本店(本多横丁入り口から移転したらしい)を発見、ここで最も豪華な五目肉まん(800円)を買い、コンビニで購入した伊藤園の玄米茶を手に入ったのが白銀町の「白銀公園」だった。
四角いスペースのフラットな公園だが、シーソー、ブランコ、球体回転機、コンクリートの小山……といった昭和的ほのぼの遊具が揃っている。ベンチに座って、そんな景色を眺めながら五目肉まんを頬張っていると、向こう方からやってきた5歳くらいの幼女と母親が目の前のシーソーで遊び始めた。
これはなんとなく恥ずかしい。若い母親の目をそれなりに意識しつつ五目肉まんをあせり気味に食べた……ということはともかくとして、その女性、年格好の割に妙におちついている。自分のことを「ママ」と言わず、「おかあさん、ちょっとつかれちゃったわ」なんて、昭和のホームドラマ調の語り口で娘と話している光景に感心してしまった。
profile

1956(昭和31)年、東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、東京ニュース通信社に入社。『週刊TVガイド』等の編集者を経てコラムニストに。主に東京や昭和、カルチャー、街歩きなどをテーマにしたエッセイを執筆している。近刊に『昭和50年代 東京日記』(平凡社)。